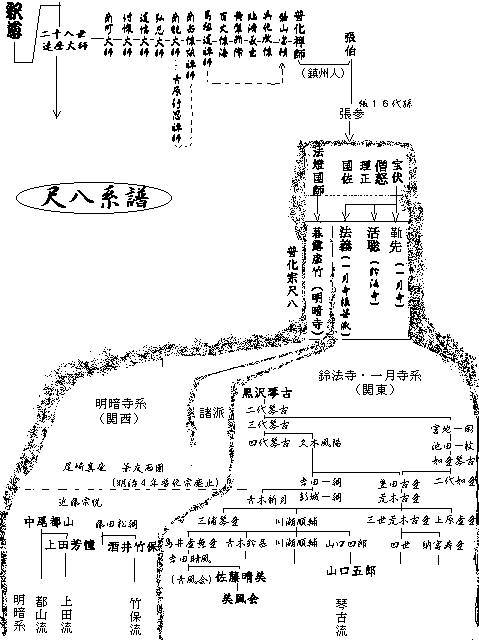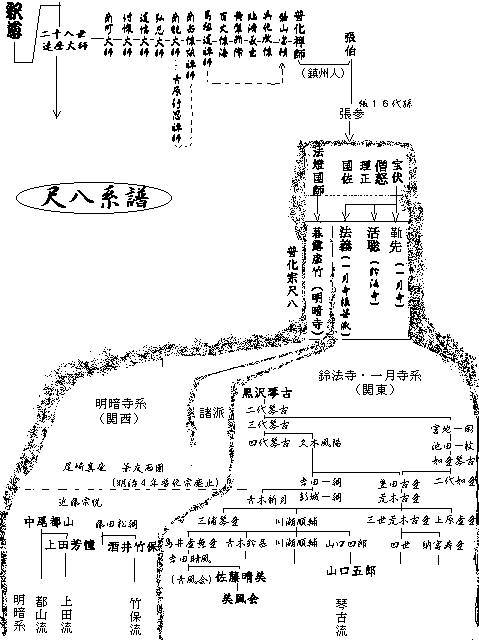
尺八の歴史
尺八の語源については諸説がある。古代中国では長さの基準に、黄鐘:(こうしょう)の音を使っていた。黄鐘(こうしょう)とは、中国の黄帝が宮廷でふく笛で、一番元となる長さの笛の音高である。
長さの基準として黒キビを90粒の長さを9寸と定めたが、この笛の音が黄鐘音である。笛は、音が同じ高さ(振動数)で有るなら、それらの笛の長さも相等しい(容積)、と言うことから笛が長さの基準として使われたのである。
尺八の名称はこの、黄鐘管の寸法をを通称名として使われるようになったといわれる。
この音から三分損益によって派生した音をつかい音階を作る。この中国の黄鐘音は日本の黄鐘(おうしき)とは違いニ(D)音となる。
この辺が非常にややこしいが、元もと中国では長さの基準として使われていた黄鐘管が、日本では一越と言う音名であったの一越が楽器の基本音のようになったので有ろうと考えられる。和音名の一越とは、ド、レ、ミのレ音である。(時代によって違いド(C)音と説く書もある)。尺八でも基本となる尺八は、一尺八寸の長さを持った筒音(ツツネ=一番下の音)が”一越”の音高の笛のことである。
唐の洞簫という笛を尺八とも言う。あるいは虚鐸とも言う。現在もはっきりした語源は分からない。
尺八は、真竹と言う種類の竹を使い、竹の表側4つ、裏孔が1つの五つの指孔を開けた楽器である。前述したように、孔を全部塞いだ場合の音はD音である。表孔が6つで裏孔が1つの7孔尺八と言うものや九孔のものもあったが基本は3孔である。
長さは一寸ごとに約半音違うので、民謡や詩吟の伴奏では、半音ずつ違う尺八を、一オクターブ分、計一二本を用いて伴奏することがある。
昨今は長管(ちょうかん)と言って二尺五寸やもっと長い、低音の尺八を使う人もいる。
尺八は流派によって歌口(吹き口)や、五孔(後ろ穴)の位置が微妙に違っている。代表的なものは、琴古流、都山流、明暗の三種である。また、尺八の構造からすると、中程で二つに分かれていて、継ぎ合わせするものと、継ぎのない1本ものにいわゆる延べという尺八がある。前者は、明治中期に一丸定吉が開発したとも言われる。
尺八の起源については、エジプトで芦の茎を使った芦笛が生まれ、それが中央アジア経由で印度に入り、そこから中国に伝わったと言われる。日本には、飛鳥以前の時代に大陸から楽人が渡来したときに尺八も含まれていたと言う。正倉院に多孔尺八が残されていることから雅楽に取り入れられていたものと考えられる。また、聖徳太子が椎坂(信貴山あたり)にて尺八を吹いていると山神が現れ舞ったと伝う。また、8世紀頃、円仁(慈覚大師)が、唐から戻ったおり持ち帰り声明に使ったという(空より声有り、”ヤ”をいれよ、とお告げがあった云々=このヤとは間合いのかけ声のようなものであろうか?)。この尺八は一節切であろう言われるが不明。この後、「伝統古典尺八覚え書」(値賀笋童著)によれば、平安時代後期(1150頃)には、雅楽には全く使われなくなって了ったという。どうなったのかというと、次第に組織が縮小されて遂には廃止された雅楽寮で人員整理された楽人達から、盲目法師・猿楽法師・田楽法師などの民間にその芸が伝えられていったと考えられる。鎌倉時代初期に出た、『教訓抄』に尺八を「今は目闇法師猿楽之を吹く」・・・・と述べられていることなどからも窺いしれる。
室町時代には一節切と言う短管の基本音が黄鐘の尺八が現れる。一休宗純がこの笛を愛好したものである。
この一節切も三味線の流行と共に廃れ、江戸時代に至ってはすっかり姿を消してしまう。替わって、現在の様な長い尺八を法器とする普化宗という組織が現れる。現在の尺八はこの普化尺八の使っていた尺八の流れを汲んでいる。尺八史を説く上で注意しなくては成らないのは、普化宗という宗教組織と尺八についての関わりについての、一種独特の思いこみの入った間違った歴史観が史実として流布しているので注意を要する。
何れにしても、普化と言う名の中国の居士の思想が、どういう訳か日本で普化宗という宗教組織として存在し、尺八が法器となり明治維新まで引き継がれたのが不思議なことです。また、法燈国師が尺八を伝えたという節もあるようですがこれも納得できない話であります。が、確かなことは江戸中期以降、普化宗という尺八を吹く集団があったと言う事実です。
この普化宗は明治4年に廃宗となり以降、宗教から解放された尺八は先輩諸師の工夫改良の結果、各方面に活躍するようになりました。