「うん、まかしとき」
「そりゃうれしいね。だって、わたし一人じゃあもったいなので、みんなにも おすそわけの約束しちゃったからね」
秋田おばあさんが、めがね越しにケン太の方をみる。
ケン太は、ニヤッと笑って野球帽をぬぐと、帽子を持った手の腕でヒタイの汗 をぬぐう。
ぬぐったあとのヒタイに、汗と汚れの、しま帯もようができました。
7月の太陽が二人をじりじり焼きます。
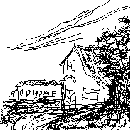
「ケンちゃんケンちゃん」
と、よぶ声がする。男の子がふりかえり
「あ、おばあちゃん」
「あ、おばあちゃん・・やないで、どないしとったんや、久しぶりやない。い
つもあわれへんさかい、さみしゅうてしょうなかったわ」
「かんにん、かんにん。なにしろいそがしいんや」
「へ」
そういっておばあさんはおおげさに、めん玉ひんむいて驚いてみせる。
背が少し低くって、細っちょで、しれで、少し腰の曲がったおばあさんの名前
は「秋田」さん。
家はケン太の通う小学校のすぐ近くの養老院です。
ケン太の5年3組の教室は、3階にあります。
教室の窓からは、こんもり茂った木々に囲まれた古い木造の協会のような屋根
だけが見えます。
ケン太とおばあさんが知り合ったきっかけは、市場の前である。
鍵っ子の健太は、学校から帰ると、いつもテーブルにおいてある硬貨をもって
市場まで走ります。
市場の前はロータリーになっていて、小さな広場があります。
広場に面したお菓子屋さんの前まで来ると、ベンチの腰掛けてはとに餌をやっ
ているおばあさんにいつも会います。
時々、おかしを食べながらエサをついばむハトを眺めます。
ある日、ケン太が見ていると
「ほれ、ぼさっとみとらんでこのえさ投げてやりなされ」
と、いってせんべい袋をケン太の方に差し出しました。
このときから、秋田おばあさんと友達になりました。
| 「ケンちゃん、あの約束だいじょうぶかい」 「うん、まかしとき」 「そりゃうれしいね。だって、わたし一人じゃあもったいなので、みんなにも おすそわけの約束しちゃったからね」 秋田おばあさんが、めがね越しにケン太の方をみる。 ケン太は、ニヤッと笑って野球帽をぬぐと、帽子を持った手の腕でヒタイの汗 をぬぐう。 ぬぐったあとのヒタイに、汗と汚れの、しま帯もようができました。 7月の太陽が二人をじりじり焼きます。 |
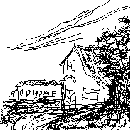 |
「これ、ケン太。汚いやないか」
「へ、へ、わすれた」
「忘れたやないがな、ほれ、そんな顔しとったらジェントルマンやないが」
秋田さんが真顔でいいながら小さな手さげバックの中から、大きなハンカチを
取りだし、逃げようとしたケン太の腕をつかんで、顔をぬぐおうとする。
づんぐりのいがぐり頭をねじるようにそらす。
「こりゃ、じぃとせんか」
「かっこ悪いからやめて」
「なに言うか。その汚い顔の方がなんぼもかっこ悪いがな」
言うが早いか、す早くケン太の顔をくしょくしょぬぐう。
「どうじゃ、サッパリしたやろ」
「うん。・・・・へ、へ、へ」
「ほれみてみ、この通りまっくろや」
と、汚れたハンカチを見せる。
「トイレで洗ってくる」
ケン太がおばあさんの手からハンカチを取ろうとすると、おばあさんは、あわ
ててバックの中にしまい込みながら、
「いらん、男の子がそんな心配せんでええ。さ、サッパリしたとこでジュース
でも飲むか」
二人はゆっこり市場の入り口横に並んだ、自動販売機で缶ジュースを買う。
もう一度ベンチに戻ると、二人並んで座って缶ジュースをのむ。
飲むとき、缶をグッと天にむかって持ち上げると、強い太陽光線がケン太の顔
いっぱいにふりそそぐ。
薄目になって太陽を見つめると、太いまつ毛の間にいくつものひかり玉が見え
る。
冷たいジュースがのどをならす。
キョウチクトウの花が咲き出している。
ケン太と秋田さんの約束は、おばあさんの誕生日に、養老院で演奏会を開くこ
とである。
[演奏会]の言いだしっぺは、ケン太と同じクラスの京子である。
六月のはじめごろ、京子が押し花にする花を探していたので、おばあさんに訪
ねてみると、養老院の中に、にたくさん花が咲いているので取りきていいよと言
ってくれたので二人で訪問したのである。
養老院の裏庭は絵本の中の花園よりきれいな花がいっぱい咲いていた。
そして、本では知らなかった、気持ちのよいかおりが、あたりいっぱいにただ
よっていた。
「うあーすてき。いっぱいもらっていい?」
京子はうちょう天になって花をつみます。
両手いっぱいに花を摘んでから少し気にして、
「何かお礼しなくっちゃ」
「いいよ、いいよ。おばあちゃんたちには、あんたたちのような、かわいいお
客さんがきてくれただけで十分なプレゼントなんだよ」
「ほんと、ほんと。ここではな、子どもは、花やチョウチョよりめずらしいん
じゃ」
近くで畑をいじっていたおじいさんが両手をおおげさに広げて
「さ、さ、建物の中にすこしはいらんか。みんなおどろきよるぞ」
ケン太が言われるままに入ろうとすると、京子が半べそ書いている。
「ま、いいさ。あんたたちのは、こんなしわくちゃの顔を見たってキショクい
いもんやあらせんからの。は、は、は」
と、秋田おばあさんは、大らかに笑い、「ちょっとまっとれや、」と建物の中
に入りました。
「京ちゃんおばあちゃんに悪いやないか」
「ごめん。ごめんだって、きみわるいもん」
言われてみると、ケン太もそう思いました。
よく見ると、木造の古い建物はすっかり表面のそろいペンキがはげ落ちてしま
っています。
ところどころに、「サラリーローン」とか、「サービス」という字の入ったベ
ニヤが、建物につぎ板がわりに張られています。
入り口の看板の文字もすっかり読めなくなっています。
「おばあちゃん、気い悪してるやろな」
「いやや、そんなの、わたし困る」
「どうする」
「うーん・・と」
京子が少し考えてから
「あ、そうや、プレゼントするの。ほれ、おばあさんの誕生日に、肩たたいて
あげるとか、ケーキをプレゼントするとか・・早々、歌うっての、どう?」
「おれ、オンチやさかい・・・」
「でも、縦笛できるでしょう?」
「うん、それぐらいなら・・・」
二人が話をしていると、秋田おばあさんが両手に大きなリンゴを二つ持って現
れました。
「さ、これあげよう」
「いい、いい」
「子どもが、遠りょするんじゃない、さ、手ださんか」
そういって、むりに二人の手の中にリンゴを押しこむ。
「ありがとうおばあちゃん」
「うん、うん」
「おばあさんの誕生日はいつ?」
と京子。
「えーと、わたしかね。ふん、ふん、ずいぶん古い話だからね・・・すっかり
忘れとったな。十月一日じゃ」
と、秋田おばあさん。
「十月一日って何曜日かしら?」
「さあね、たしか、日曜日じゃったかな・・」
「よかった。あにね、わたしたとち、おばあさんの誕生日に演奏のプレゼント
しょうって言ってたの」
「京ちゃん・・・」
慌ててケン太は、京子の言葉をさえぎろうとしたが、
「おやま、それはうれしいね」
と、秋田おばあさん。
養老院を出てからのケン太はプリプリ。
「ケンちゃん、だいじょうぶって、わたし友達にも手伝ってもらうから心配し
ないで」
京子の言葉に少しは安心したものの、やはり少し心配だった。
しかし、京子の言うとおりであった。
京子の呼びかけに、二、三日すると、クラスの5人が加わってくれることに決
まった。
それだけではありません、京子の担任の中村先生も協力してくれることになっ
たのです。
編成は、ケン太と黒木君、田中さんが縦笛です。井上君がピアニカ。そして、
高木さんと村井さんがフォーク・ギーターで、亨子ちゃんが養老院のこわれかか
ったオルガンです。
中村先生は、指揮者けん打楽器です。
練習は夏休みに入って、始まりました。
練習は最初の頃は、みんなで話ばかりして、なかなか練習できませんでしたが
、二学期が始まる頃には曲らしくなってきました。
二学期も始まり、秋田おばあさんの誕生日まで、あと10日ほどになりました
。
ほうか後、ケン太が下校しようと下駄箱で靴をはきかえていたとき、中村先生
が足早に近づいてきて、
「ケン太、わるい、わるい。実はイモンのことだけど、先生、急用ができて行
けなくなったしまった」
ケン太は突然のことにどう返事をしていいのかわからない。
「ま、君たちが決めたことだから、先生が参加するよりみんなの自主てきな行
動に任せた方がねうちあるさかいな。は、は、は」
そういって去っていく先生の後ろ姿をただぼんやりケン太は見送っていました
。
本当のところ、ケン太の気持ちとしては、中村先生が参加してくれたとき、”
全面てき”に先生が柱になってくれたと考えていたのです。その先生が、「あ、
は、は、」と笑いながら去ってしまったのです。
家に帰ったケン太は、誰もいない部屋の中がいつもより広く感じられました。
机の上のお小遣いもそのままにしごろんとタタミのうえで、大の字になりまし
た。
もし、市場に行って飽きたおばあさんに会えば、どう言えばいいのかわかりま
せん。
しばらくぼんやりしていましたが、急に京子ちゃんの顔が思いうかびました。
電話をします。
「あ、ケンちゃん。うん、わたし大じょうぶよ。そうそう、でも、井上さんと
、黒木さん用事があって参加できないって。いまごろね・・。連絡遅れてごめん
ね。でも、何とかなるわ。わたし少し急いでいるの、またね」ガチャン!!
受話器の切れる音が、ケン太の頭の中でこだましました。
ケン太は指を折って人数を数えます。
(中村先生と、井上君、と黒木君がでめで、残りは田中さん、高木さん、村井
さん、亨子ちゃんとボクで五人か。ま、いいか)
せっかくの練習が非違になってしまいそうですが何とかいけそうにも思えまし
た。
でも、ケン太は中村先生がひどく憎らしく思いました。井上君、黒木君の欠席
が先生のせいで引き起こされ足されたように思えたからです。
いよいよ明日がイモン日のことです。
ケン太が夕食をしているときに電話が鳴りました。
お母さんが受話器を取ります。
「あ、ケン太ね。ちょっと待ってね。・・ケン太、京子ちゃんからよ」
「もしもし、変わりました・・・」
「あ、ケンちゃん、ごめん、ごめん。わたし急用ができちゃって明日行けない
の。本当は行きたい気持ちでいっぱいよ。でも、重要な用事なの、ごめんね。そ
れにね、わたしが行けないって言ったら、高木さんと村井さんも行かないって言
うの。無責任でしょ。ごめんね・・・」
「・・・・もういい」
そういって、ケン太は受話器を荒々しく下ろしました。
「ケン太どうしたの」
お母さんの声が背中のほうでしたとたん、ケン太の目から大粒の涙がこぼれ落
ちました。
「おい、ケン太。お母さんが何か言ったのだろ、返事をしなさい」
食卓で新聞を広げていたお父さんの声がしました。
ケン太が無言で立っていると、母の立ち上がるケハイがしました。
「も、どうしたの、泣いているの?」
顔をのぞき込んだお母さんのスットンキョウな声。
「泣いてるか!、このクソババーあっち行け!」
お母さんの胸あたりをこぶしでたたくと、隣の部屋かけこんで、ふすまをバタ
ンと閉めました。
カーテンの閉まった室内は電灯もついていなくて暗いままです。ケン太にはい
つもより室内が暗く感じられました。
暗さは、部屋の中だけではなく、ケン太の心奥にまでずーっと続いていました
。
ひんやりした畳の上で泣いていたケン太はいつの間にか寝入っていました。
ケン太が目をさますとふとん中にいました。
閉じられたカーテンのすき間から、朝日が部屋の奥にむかってまばゆいひかり
の帯を描いていました。
寝ている間に、ケン太の心も静かになっていました。
−−そうだ、田中さんがいたっけ−−
ケン太はそう思い出して、急いで田中さんの家に電話をしました。
受話器の向こうから男の人の太い声がしました。
「きのうから、京都の親戚に泊まりにいっていないよ」
冷たい返事が戻ります。
「これ、ケン太いつまで寝ているの、起きなさい。お母さんふとん、ほしたい
のよ」
「・・・・・」
「それに、ほれ、何とかのおばあちゃんのイモンじゃあなかったの」
「・・・・」
「どうしたのさっさとおきなさい」
ケン太は黙ったままふとんに頭ごと潜り込んでいっこうに起きようとしない。
時々、ふとんの中から鼻をすする音がきこえる。
お母さんは、そっと部屋から立ち去りました。
昼頃です。
ケン太の家の玄関でチャイムが鳴りました。お客です。
母の声がして、玄関をあがるもの音がしました。
「これ、ケンちゃん、いつまで寝とる!」
急に大きな声がしました。秋田おばあちゃんの声である。
ケン太は、少しだけふとんから顔をのぞかせ、また、すぐにもぐり込む。
「こりゃ、約束すっぽかして昼寝なんぞしくさって、なんじゃい」
起こったような言い方である。
「・・・・」
「えーい、そーれ」
おばあちゃんがかけ布団を勢いよくはねのける。
フトンのまん中でいも虫のように丸まったケン太があらわれる。
「な、なにすんねん」
ケン太があわててフトンを取り戻そうと、腕を二、三度空に向かって振り回す
。
「なにすんねんて、そら、こっちの言いたいせりふや。約束どうした」
そう言われたとたん、ケン太が起きあがり、フトンの上に正座する。
「・・・みんな、みんなが悪いんや。約束やぶりやがって・・」
「なにが、み・ん・な・や。み・ん・な・は、みんなや。ケン太は、ケン太や
」
「そやかて、お、おれ一人でできへん」
「なんや、ほんなら、まかしとき言うてたんは、ひと様のフンドシあてにして
偉そうな口言うとったんかいな。おばあちゃん、ケン太のま心かいなと思っとっ
たんやけど、えらい思いちがいやった。他人様のもん、あてがうつもりやったら
、このおばあちゃん、願い下げや」
「そんなことない」
「そんならなんでや」
「おれ、一生けん命練習したんや」
「一生けん命した言うたかて、けっきょく、ひと様あてにしとったんやろ」
「そら、合奏やさかい」
「それでも、ひと様の宛ができんようになったんやろ」
「うん」
ケン太がうなずく。
秋田おばあさんは、ケン太のお母さんが運んできたお茶を一口、おいしそうに
すすってから、
「その、人があてにできんやったら、自分で一人でせなしょうないのとちがう
か。それが約束やろ人間はな他人様あてにするのもいいけど、最悪の時は自分一
人ででもするカクゴがなかったらなにもできんのや。そんな、心がまえのうてな
んで、ひと様のイモンなんぞできるのや、なんで、ひとりぼっちの人の気持ちが
分かるのや」
「・・でも、おれ、へたや・・・で・・」
上身づかいに秋田おばあさんの顔を見る。
「ミソ、腐ってもええか」
「ええ、ええ。そんなモン安いモンや、なんぼでも買ったるがな」
ケン太は、急いで机の引き出しから、たて笛を取りだす。
「おばあちゃん、うしろ向いとって」
「なんやて」
秋田おばあさんがとぼけた振りして聞き返す。
「ええから、はよ向いて」
「はいはい、わかりました」
ケン太は、後ろ向きになった秋田おばあさんの方に向いて、一生けん命笛を吹
きました。
吹き終わったケン太の顔は汗でグッショリだった。
窓の外から吹き込んできた風が、上気したケン太の顔を心地よく冷やす。
それは、また、ケン太の心の中まで、さわやかにしてくれる。
秋田おばあさんは、ケン太に背を向けたままこっくりこっくり船をこいでいた
。
おしまい