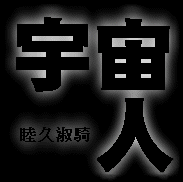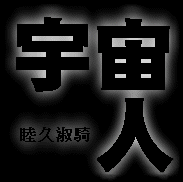|
私は宇宙人である−と言っても誰も信じないだろう。もっともなことだ。私の外見は一般の地球人とほとんど違っていない。いや、地球人そのものなのだ。私はある星から派遣された地球調査員としてその目的を遂げるために、一人の男とそっくりそのままに私の体を変身させ、その男は原子単位にまで分解してしまって、まんまと入れ替わってしまったのである。その地球人の男自身の肉体的な面は何ら変わってはいない。しかし私は今まで通り彼の性格を受け継いで、ごく自然に生活してゆかねばならない。私が宇宙人であるという身分を明かすことができないのは、この地球人の社会でそんなことをすれぱ、すぐに気違い扱いされて精神病院行き…なんてことになってしまったら最後、地球人の文化や社会を観察することができなくなってしまうからだ。私の任務は、この地球という惑星を調査し、我々の植民地として適当かどうかを母星に報告することなのだ。
そんなわけで、私の生活は普通の人間とは全く変わらない平凡なものだが、地球人に変身しているのは私にとってかなり窮屈なので、時々人目のないところでは元の姿に戻っている。やはり眼は三つあったほうがいいし、手足も四本ずつなけれぱどうも不便を感じてしまう。
だが、それがいけなかった。ある晩自宅で元の姿に戻っていたところを、隣りのオバサンに見られてしまったのだ。私はすぐに変身しなおしたがもう遅かった。そのオバサンは口をポカンと開いたまま、声を出すことも出来ずにつっ立っている。くそっ…まあいいさ。いくら怪物だと言って騒ぎたてたところで誰も本気になんかしやしない。どうって事ないだろう。そう思って平然としていたが、次の瞬間にその中年女から発せられた言葉は私の思いもかけぬものであった。
「あなた、CA−104星人じやないの?」
彼女はハッキリと、我々の使用している銀河系標準語でそう言ったのだ。CA−104星とは私の母星のことだ。
「どうしてそんなことを知ってるんだ?君は誰だ?」と私が聞き返すと、
「ご覧の通りよ」そう言って女は変身…いや、元の姿−大きな複眼に、長いシッポを持った、猿のような生物−に戻り始めた。
「ややっ、君は…XS−58星人ではないか。どうしてこんな所に…」
「地球の植民地化のための事前調査よ」
「君の星もそんなことをやっているのか。しかし隣りのオバサンがXS−58星人だとは気がつかなかった」
「こっちだって同じだわ」
その時、我々の銀河系標準語を聞きつけて今度は向いのダンナがやって来た。銀河系標準語は地球人の可聴周波数の範囲をはるかに越えているから、普通の地球人には聞こえないはず…とするとこのダンナも…。まさしくダンナは我々を見て大声をあげた。
「わっ、CA−104星人とXS−58星人じゃないか」そしてダンナも、六本足のカエルのような本来の姿に戻った。
この騒ぎに私の家族が気づかないはずがない。みんな集まってきて、これも驚いたことに、おじいちゃんから、まだ2ヵ月にしかならない赤ン坊までが次々に元のいろいろな姿に戻って、
「そこにいるのはTU−3309星人ではないか!」
「ぎやっ、VB−01星人だ!」
「NN−88星人もいる!」などと仰天しながら、口口にわめき出すのである。騒ぎはますます大きくなってゆく。しかも集まってくる者が、みんな銀河系内に散在している星々の住人なのだ。話を聞いてみると、みんながみんな、地球を植民地化するための調査を目的として地球へやって来て、私と同じように、地球人になりすましていたというのだ。そのうちに全員がめいめい自分の先優権を主張し出して、私の家は大混乱の場となり始めた。
それでも、やって来る宇宙人は増すばかり。最後には、銀河系の星々の生物たちがそれぞれ一人ずつ、みんな勢ぞろいしてしまった。考えてみれば、銀河系内に残っている植民可能な低文明惑星は、この地球しかないのだから無理もない。
そして、あたりを見回してみると…みんな宇宙人ばかりで、もう地球人は一人も残ってはいなかった。
〈終わり…その1〉
本編はここで終わってしまってもいいのだが、感動のあまりに、まだ読みたいと思っている人もあるだろう。SFについて理解を深く持っておられる方ほど、おそらくそうだろうと思う。そんな方は続きをどうぞ!
「くそおーっ、我々はみんなで作り上げた偽造の社会とも知らずに、いっしょうけんめいに調査していただけなのか!地球人が、本当はみんな宇宙人の変身だったなんてこれじや何にもならない」
宇宙人たちが口々にくやしがっているとき、地球はすでに強力なバリアで囲まれていた。そのバリアの外で一個の知性体がつぶやいた。
「これで夏休みの宇宙生物採集ができたぞ。この小宇宙の生物はみんな下等だから、集めるのが楽だったな。ちっぽけな惑星一つをワナにすれば、みんな集まってくるんだから」
そう言って彼は、銀河系の知的生物の標本箱みたいな地球を引っぱりながら、アンドロメダ星雲の方へと向って行った。次の獲物をねらって…
〈本当の終わり〉
|