I.ジュリアード弦楽四重奏団・ベートーヴェン弦楽四重奏曲全曲演奏会
第7番 へ長調 作品59の1 《ラズモフスキー第1番》
第13番 変ロ長調 作品130 《大フーガ付》
いつだったか、演奏会の折りにもらったチラシの中に、ジュリアード四重奏団によるベートーヴェン弦楽四重奏全曲演奏会のものが入っていた。カザルスホール10周年記念企画と銘打ってあったが、ジュリアードにとっても特別の演奏会になるものだった。それは、このあと創立以来第一ヴァイオリンをつとめてきたロバート・マンがその地位を離れるからだ。
思えば私がジュリアード四重奏団の名を初めて耳にしたのは大学に入ってからで、1960年代から70年代、彼らが弦楽四重奏の演奏史を塗り替えて行くような活躍をしていた頃だ。バルトークの弦楽四重奏曲全曲、ベートーヴェンの弦楽四重奏曲全曲といった大物が続々とレコードで出されて来ていた。
もっとも弦楽四重奏演奏史ということになれば、ジュリアードの前にブダペストの名をあげなければならない。彼らには19世紀的演奏様式を20世紀的演奏様式に引き上げた、という評価が下されている。そのブダペスト四重奏団によるベートーヴェンのレコードが出たときも大変な驚きだったらしいが、ジュリアードは早くもそれを越える印象を与えたようだ。1970年出版の「今日の演奏と演奏家」の中で吉田秀和氏はこう書いている。
「私は、これまで《ラズモフスキー》ではブダペスト四重奏団以上の名演を聴いたことがないし、またそれ以上のものを自分の耳に経験することがあろうとは期待もしていなかった。しかしジュリアード四重奏団の演奏に比べれば、ブダペストのはダイナミックな迫力という点では、もう完全に 凌駕されている.....」
ジュリアードに比べるともうブダペストの演奏は「古典」に入りつつあるとも言っている。要するに、ジュリアード四重奏団は、時に機械的と言われる程に正確無比、交響的ともいえるダイナミックス、激しい緊張感と快速なテンポ、メンバー内の徹底した平等性等々で、極めて現代的な演奏という訳だ。
この現代を代表する弦楽四重奏団も早50年、しかも中心人物のロバート・マンが引退するという。この最後の機会に是非実際の演奏を聴いてみたいと思った。ただし、これまで、私自身はこの団体のよき聴き手であった訳ではない。手元にも、バルトーク、シェーンベルク物、それにベートーヴェン中期があるだけだ。バルトークは凄いと思ったが、それは曲自体の印象も入っていたし、その後ハンガリー四重奏団の全曲演奏会を聴くことが出来てそれで満足してしまい、ジュリアードのは一枚手に入れたままになっている。
ベートーヴェン中期は吉田氏の評を読んで買ったと思う。《ラズモフスキー》第1番には確かに仰天した。吉田氏の評が一つ一つ当てはまるのも、まさしくこの曲といえる。スケールの大きさ(それは雄渾という言葉がぴったり)、演奏の正確さ(決して機械的ではない)、緊迫した運び(一瞬一瞬の充実)、どこをとっても名演の名に恥じるところはあるまい。しかしこのような名演を引き出すほどにベートーヴェンのこの曲は見事な曲だ、というのも真実ではあろう。
とにかくこの印象はしっかり心に刻まれていて、今回の演奏会でもこの曲は必ず聴こうと思っていた。それは6月3日、この日の曲目は《ラズモフスキー》第1番と第13番大フーガ付きだ。後者についてもしぱらく前から気になっていたところがあったので、私には絶好のプログラムであった。
さて少し前置きが長くなったが、いよいよその当夜。まず演奏に先立ってヴィオラのS.ローズ氏のレクチャーがあった(これは今回の連続演奏会では毎夜行われた)。こういうことは余り無いようにも思うが、そういえばこの団体は教育方面の活動もしていて、彼らのもとからラサール四重奏団や東京四重奏団が育っていることは知られている。今回のレクチャーは一寸した啓蒙活動といったところか。
お目当ての《ラズモフスキー》第1番から始まったが、正直なところ、レコードで作られたイメージと大分違っていたので少々面食らってしまった。50年の歳月によるものか、はたまたメンバー交替によるものか(ロバート・マンを除いてしばしばメンバーが交代したことでも知られている)、あの「現代的」演奏はどこへ行ったのか、大分ソフトなものになってしまっている。
特にジョエル・クロスニックのチェロがよく響いて、しかもそれが明確に強く、ではなくて、焦点の定まらないボンヤリ・フンワリした感じで、これが随分雰囲気を柔らかいものにしているようだ。ヴィオラもレコードの方はラファエル・ヒリヤー、これは快刀乱麻を断つのおもむきで、なまじのヴァイオリンよりはるかにうまい。これに対しS・ローズの方はそこまでの明快さは無い。これはもう、かつてのとは別の演奏であり、別の解釈であろうが、それではどんな解釈なのか、つかみあぐねているうちに曲は終わってしまった。
二曲目の第13番、今回の演奏会では、終楽章が大フーガによるものと、後作のアレグロによるものと、二回演奏しているところが面白い。この夜は大フーガ付きの方だ。この13番という曲は以前は面白い曲と思ったこともあったが、このところよく分からなくなった感じで、その中でも大フーガ。そもそもこの曲は弦楽四重奏で演奏可能な曲なのか大きな疑問だ。スメタナ四重奏団で聴いても、ブダペスト四重奏団で聴いても、アルバン・ベルク四重奏団は実演で聴いてみたが、いずれも弦が悲鳴をあげているように聴こえてしまう。一体19世紀前半にどうしてこの様な曲が生まれたのか。後期のベートーヴェンでは、しばしば時代離れした響きが出現するが、これはその中でも際立っていよう。
ローズ氏のレクチャーでも、ベートーヴェンはこの曲を未来の聴き手のために書いたと言った、と言っていたが、その未来はいつなのか。半音階と跳躍した音とを組み合わせたじつに奇妙なテーマ、すさまじい不協和音、激しく殆ど狂気に満ちた音と音の衝突、とりわけきしむような音・音・音と一転してトニカ和音の明快さと快速な三連符のリズムによる心地よい運びがどう調和するのか、見事な終結にもかかわらず曲後も腑に落ちないものがコダマしている。
この感じはジュリアード四重奏団の演奏を聴いても拭えるものではなかった。ただそれにしては無難に曲をまとめていた印象はある。曲の終結もいろいろ聴いた中では、一番よかった様に思う。しかし振り返ってみても、大フーガはそもそも弦楽器四丁では負担が大きすぎる、ということはいえると思う。大フーガが時に弦楽合奏で演奏される、というのも頷ける気がする。私としてはこの方面をもっと深ってみたいと思っている。
II.アルバン・ベルク弦楽四重奏団・シューベルト生誕200周年によせて
弦楽四重奏曲 第12番 ハ短調 D.703 「四重奏断章」
弦楽四重奏曲 第13番 イ短調 D.804 「ロザムンデ」
弦楽四重奏曲 第15番 ト長調 D.887
アルバン・ベルクの演奏会は二度目だ。何で見かけたのか、ジュリアード四重奏団演奏会の前後をそれとなく調べていたら目に入り、この機会を逃す手は無いと、一日休みを多くとり、二夜連続の弦楽四重奏鑑賞会とは相成った。
前回は池袋の東京芸術劇場大ホールで聴いた。ホール内はなかなか、凝った装置が施してあって面白いが、いかににアルバン・ベルク四重奏団がスケールの大きい演奏をするといっても、それにしても会場が大きすぎる。細かいニュアンスなど一寸聴き取りにくい。今回のホールはピアノ演奏では既に経験済み、大変よかったが、弦の四重奏も悪くなかった。デリケートな部分も十分伝わって来た。
四重奏断章も第15番も、いわば表現主義的な極めて強烈な表情・表出で共通性がある。一方第13番は旋律中心で、いかにもシューベルトらしい。「いかにも」と、ふと書いてしまったが、しかしよく考えてみると「シューベルトらしい」とはどういうものか。抒情的な美しい旋律による音楽をなんとなく「シューベルト的」と思っていたが、案外シューベルトはケレン味のある曲を書くこともあって、いわば「かっこよさ」をぐいぐい押し出してくるところもある、作曲上のスタイリストとでもいうか。これがさらに進むと、上記のような「表現主義」になるのか、どうなのか。
恐らくシューベルトを正当に評価するには、あの膨大な歌曲群を聴いていなければだめだと思うが、この点ではわたしは失格といわざるをえない。アルバン・ベルク四重奏団は第13番も表現主義的演奏で通そうとしているかのようだ。特に第一楽章、憂鬱そうに始まる第二ヴァイオリンの音型、そして支えの伴奏ヴィオラとチェロは特色あるリズムを刻んでいる。弱く
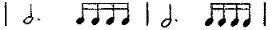
と打たれるリズムは、いうなればシューベルトの運命の扉か。ベートーヴェンでは運命の扉は強く激しく
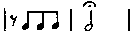
と叩かれるが、シューベルトの方は実にひっそりと。こう考えると第三楽章の冒頭
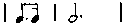
もシューベルト的運命の扉として付け加えたくなる。第一楽章はアレグロ・マ・ノン・トロッポだ。にも拘らずアルバン・ベルクは実に速い。かぼそい

など消し飛んでしまっている。テンポの安定もいささか失われている。というよりそういう表現を目指していない、ということなのだろう。
以前他の団体でもこの13番を聴いたことがあるが、その時もテンポの速さに驚いたことがある。わたしの耳にはどうしても繰り返し繰り返し聴いた(テープが伸びる程に)プラハ四重奏団のものが染み付いてしまっていて、この速いテンポにはついていけない。もっと素朴な感じでじっくり歌わせ、その陰で不安をそそる独特なリズムをひそやかに鳴らしてもらいたいのだ。今回のどちらの演奏会でも、どうも既に耳に居着いてしまったイメージが新たな演奏を受け容れず、衝突を起こしているケースが多いようだ。
第二楽章は、この曲の「ロザムンデ」のあだ名の由来になったテーマで構成されている。これもアンダンテにしては速い。今回演奏会の前に気に入った曲のスコアを入手して少しばかりながめていたのだが、この13番には驚いた。イ短調、ハ長調という調性もあろうが、スコアは一瞬学生用の優しい練習曲かと思うほど(もっとも弦楽四重奏にピアノのバイエルやツェルニーのような練習曲があるのか知らないが)簡潔簡明なものだ。変化記号も少なく、こんな平明な楽譜からどうしてあのような滋味のある音楽が響いてくるのかと、改めて驚きを感ずる。
演奏の方は第三、第四と楽章が進むにつれて落ち着いた雰囲気になって来て、特に第四楽章は村の踊りを描いたかといった楽しい雰囲気で、デュナミークもそれほど大きくなく、演奏と曲の内容とがよくマッチしていた。それだけに第一楽章の解釈には疑問が残った。
第15番、強く細かいトレモロ、長調というがたちまち短調に折り込まれ極めて不安定、全楽器の斉奏、それもリズムの激しい部分で、といった語法が随所に現れ、そんな部分はまさしく表現主義的といってよい。しかし、では何を表現するのか。旋律は断片的、そして執拗に繰り返している感が強く、発展とか展開とかいうところが余り見られない。
中では第二楽章は面白かったが、しかし少々長すぎる。第四楽章、不自由なテーマ、ノビノビの逆で常に拘束を感じさせる表現。全楽章を通して休まるところのない曲てあった。どうも効果だけが優先されているような曲で余り好きにはなれないが、それでもアルバン・ベルク四重奏団の演奏が、技巧だけではない何かがあるように感じさせた点は、付け加えておこう。
(1997.7.31)