一休さんと言えば、とんち話で有名ですが、この一休さんこと、一休宗純はと てもこの笛を愛好していたようです。
一休さんは、京都/大徳寺の真珠庵(元瞎驢庵:かつろあん)や、大阪・枚方と宇治に隣接した田辺町の 酬思庵に住まわれていた、室町時代の戦乱時代のお坊さんです。
「狂雲集」の中に尺八の詩を多く残されています。
![]() 右の笛は、一節切尺八です。
右の笛は、一節切尺八です。
一休さんと言えば、とんち話で有名ですが、この一休さんこと、一休宗純はと てもこの笛を愛好していたようです。
一休さんは、京都/大徳寺の真珠庵(元瞎驢庵:かつろあん)や、大阪・枚方と宇治に隣接した田辺町の
酬思庵に住まわれていた、室町時代の戦乱時代のお坊さんです。
「狂雲集」の中に尺八の詩を多く残されています。

飄零狂客也何之
十字街頭笛一枝
多病残生無気力
新吟慚愧老来詩
右の写真は一節切に書かれている文字
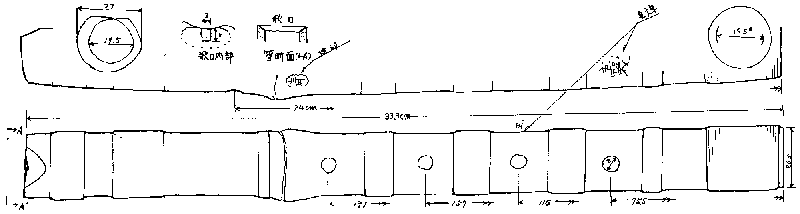 |
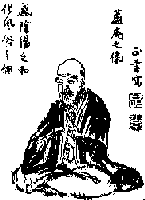 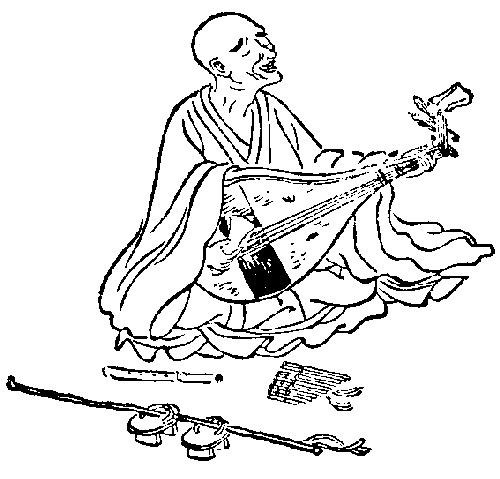 左側は「糸竹古今集」と言う指田流一節切伝の本の扉絵です。(天理図書館蔵) 右は、四面七十一番職人歌合の図 足下の笛は一節切か? |
| これは、”一閑先生「尺八筆記」”と言う江戸時代の本の中の、一節切の部分
です。一閑とは、初代黒沢琴古の門人宮池一閑のことです。(国会図書館蔵) この図では、「小竹」と言う後期の改良型、あるいは、「天吹」と言うもので はないかと思われます。 |
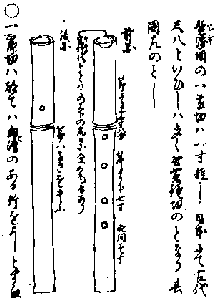 |
一休さんこと、一休宗純が現在伝わっている普化尺八(ふけしゃくはち)の始祖ではないかとも言われています。
この訳は、いろいろな伝説に出てくる話が一休さんの足跡、行状と似ているからです。
たとえば宇治辺で芦庵(別の字の場合もあります)という老人が尺八を吹いていた、とか「糸竹古今集」(このページの右上挿し絵参照)にある廬庵図であるとか、ちょうど一休さんが5、60才の頃、京都の大徳寺内にあるかつ驢(ろ)庵(ろとはロバのこと=目の見えない=>おろかと言う意味でしょうか。ここで重要な驢について言えば、臨済録に、普化が生菜を食べているのを見て、ロバに大いに似ていると言ったところ、普化はロバが嘶く真似をしたので罵ると、彼も罵り返した)と言うところにおられ、京都と奈良の中間当たりの木津川に沿ったところ、薪村にある現在通称一休寺と言うお寺の再興のために通われていました。こういったことの他にも多くの似た話が伝わっています。
ここで木津川について少しふれますが、現在、この川は京都府橋本市で桂川、宇治川と合流して淀川になっています。この合流点の宇治川には、かって江戸の少し前までは、巨椋(おぐら)池と言う巨大な池がありそこに流れがはいっていたのです。そのために、人々は、京都から奈良方面に向かうには、この池を迂回して宇治廻りの街道を使っていたようです。
また、尺八の始祖が悟りをひらいたときの話に、「闇夜に鳥のカラスの啼く声を聞いて悟った」というのもあったようですが、実は一休さんも琵琶湖の堅田で悟りをはらいたきっかけは孤舟(琵琶湖畔)で深夜啼く鴉の声を聞いたときだそうです。また、自らを狂雲子と称したり、師である華叟の教えを次ぐ者は自分のみだと言っていました。
自ら尺八も吹かれていました。
室町時代の南蛮貿易港、大阪・堺にもよく行かれていたようです。大徳寺伽藍再興を引き受けた堺の豪商と言われた尾和四郎左衛門(一休さんに私淑して法名:宗臨、をもらった)の関係を考えれば、一節切尺八を入手する事も容易なことがわかります。
一休さんの活躍した室町時代は下克上の時代でもあり、奈良時代に渡来して平安時代に花開いた貴族文化を打ち壊し、新たな文化を積極的に受け入れた時代でもあります。
尺八もこのころ、雅楽尺八(正倉院等に残っている縦笛)とは全く違った新たな縦笛として渡来したのが一節切だったとも考えられます。
もう一つの検証としては、一節切が黄鐘切りとも言われることです。黄鐘(おうしき)は、日本の十二律で言うなら、A(ラ)の音程の管のことです。実際吹いてみると、筒音(全部孔を塞いだときの音)はラの音です。しかし、中国から渡来したとするなら、黄鐘は”こうしょう”(日本読み)”のことであり、D音で無ければおかしいわけです。即ち日本の律名でいうなら、音の高さが同じなら、一越でなければならないわけです。
「黄鐘」という文字に注目すれるなら、中国(あるいは大陸)の黄鐘(こうしょう)の楽器を、文献などを頼りに、日本では黄鐘(おうし)の笛と間違った解釈で作ってしまったのではないでしょうか。とすれば一節切は、日本で独自に作られた笛と言うことになります。
このほか、一節切尺八は、音域の狭い尺八ですので、独奏あるいは単独で演奏する分には問題が無かったのですが、三味線が渡来し広く流布、箏等と合奏するように成ってくると、琴や三味線は中元の基準が一越(黄鐘:こうしょう=D音)で有るので一節切尺八の音域とがかみ合いません。このために、三曲合奏が盛んになるとともに、一節切(黄鐘=A)が消え、一越(筒音)の普化尺八(一越=D)に改良された笛を生むことになったとも推測できます。