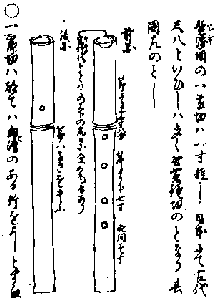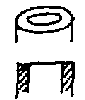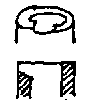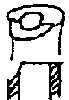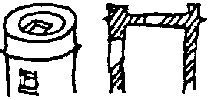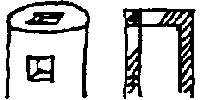これは、現存の尺八と全く同じく根竹を用い節の近い頗る支夫なむので、従来の歴史では、江戸後期に著されたと考えられる「虚鐸伝記国字解」なる書物に記されたところの内容を持って不動の各説と信じられて来たが、琴古流尺八家中塚竹禅師が、昭和ll年から14年までに渉り雑誌「三曲」(現在の日本音楽の前身)に「琴古流尺八史観」の題名で上記の説を教種の資科により、後世の偽書であると断定iしたが、残念なことに同氏は上記「史観」の結論を出す事なく不帰の人となった。
2・虚鐸傅記国字解の伝説内容
鎌倉時代初期信州の僧覚心が、宋に留学中、同窓の学友張参が珍しい尺八曲をつたえていたので、その曲を学んで帰朝したのが普化尺八の伝来である。
この張参の教えた曲は、張参16代の祖河南の張伯が唐の高憎の普化禅師が、常に鐸(タク・振鈴)を振って市中を説教し
「明頭来明頭打、暗頭来暗頭打、四方八曲来旋風打、虚空来連架打」
の禅句を称えた。
張伯これを慕って入門を乞うたが計されず、神師の去った後も、虚空から鐸の音が、びびいて来るのを尺八を以て「虚鈴](戒いは真虚霊とも鈴慕ともいう)を作曲したが、これの子孫が張参につたわったと言い、また、覚心は帰朝の際一緒
に宝伏・国佐・理正・憎怒の四名の普化僧も来朝して尺八の普及を応援した。
二とに、宝伏は尺八を尤もよくした。
覚心は、帰朝後紀州由良の興国寺の開祖となり没後法燈国師と諡された覚心の高弟寄竹は、行脚の途次、伊勢朝熊山頂で仮眠中に「霧深い海中にて妙音を聞き、霧晴れて後、再び虚空に妙音を聞いたので、これを基にして作曲じたのが霧海
寄竹は、後に京都白河に虚霊山明暗寺を作って住居したが、これが関西普化宗本山である。
寄竹は後に虚竹と改名した。覚心と共に来朝した宝伏門人金売(
以後、正勝は、他人に姓名を尋ねられると、単に虚無とのみ答えたので、人々これを虚無僧と称した。
これが虚無僧の始まりである。
3.中塚竹禅氏の反論要旨
始め、同氏は琴占流尺八史の史料蒐集の目的で、由良の興国寺にて資料を調査したところ、覚心の在宋中の日記、帰朝後の日記・書簡等に、尺八の事は一言も記されていないし、寄竹の存在も不明であり、宝伏等四名の来朝者も単なる雑役夫で、尺八に長じた事実は見当たらない。
明暗寺は、鎌倉峙代に出来たのではなく、江戸時代初期までは、薦僧の宿伯所にすきなかった、それを寺にしたのは江戸時代である。
また、普化宗と言う宗派は中国に存在しない(但し普化禅師なる禅憎は存在する)普化宗門の信条である「慶長掟書」(徳川家康自筆の虚無僧許可並ぴに保護状)は、原本焼失と称して実在せず写しは各個に文章の相達がある。その他、中国の音楽に「虚鈴」と言う尺八曲は見当たらない。
「虚鐸伝記国字解」の原本であるべき「虚鐸伝記」と言う、漢文の書籍が存在しない。
楠正勝が、尺八を吹いた事実も歴史に見当たらない。
等々の反証が有り「虚鐸伝記国字解」は偽書であるから、信用出来ないと言うのが、現存の日本音楽史研究家の説となった。
4.普化尺八本当の歩みの推測
室町峙代の薦僧の発生は前述したが、戦国の世となって武家の浪人も、また薦憎となるものが多くなった。大森宗勲以後、技も著しく向上して江戸時代になると、いっか「古傅三曲」が現れた(これは宗勲あたりの作曲ではないかと言われる)江戸幕府は、次第に浪人の取り締まりを厳しくしたので、浪人等は生活を脅かさ
れるので、相計って生活保護の為一種の宗団を作り普化宗と名付けたが、真の僧侶てはないから、経典には通ぜず一節切により生活を維持し行脚する事にしたが、当時、一節切は普及しすぎているので、尺八と改称し、雅楽尺八に似せて管の長さを一尺八寸に改め護身用として根本の太い竹を用いた。
然して、宗団の本山として明暗寺を人手したが、切支丹の取り締まりが厳しい折から新寺の建立は許されなかったので、興国寺の未寺に席を置いた。
この頃「虚鐸伝記国字解」が作製されたらしい。なお、[慶長掟書]を偽作して寺社奉行に提出したが、幕府は浪人取り締まりの一助と考え偽書を黙認して許可し、その交換条件として浪人取り締まりと、その情報提供を課した。
それで本山が、京都では不便な処から関東総本山を、小金の一月寺と青梅の鈴法寺とし、両寺の事務所を、江戸浅草付近に設置して幕府の連絡に当てた。
以後、普化宗は公認の宗教となり、虚無僧の地位は安定した。
また、天蓋で顔を蔽ひ隠す風俗は、徳川四代将軍以降の事であるらしい。
以来一月寺、鈴法寺の住職は、尺八の技よりも幕府との折渉が任務となり、尺八指南は、別に寺侍として所属した、この中から黒沢琴古(黒田美濃守の臣)のような名手が出て琴古流の源となる。
要するに普化尺八は、一節切が江戸時代初期に日本で改造されて出来たものと推測される。
5.天吹(テンプク)
節は、中間に三ケで、根竹を用いず一節切に似ている唄口は、尺八に似た切り方である。
朝鮮の短簫にも似ている滅亡寸前の物で、一節切と尺八との中間のものである。
これが、今少し解明されると、我が国尺八発生の状況が、詳らかになるかも知れない。(鹿児島県にのみ現存する)