|
[strong-men:番外]大和スキャナー(前座その3)
飛行機の設計に流体力学を応用する手法は、
海中を前進しながら沈んだり、浮上したりする物体の設計にも
使えるのではないか?
航空機の世界で、グライダーは1メートル
降下する間に30メートル先まで進みます。
こういうのを滑空比30:1とか滑空比30といいます。
性能の良いものになると50〜60というのもあるそうです。
滑空比30のグライダーの降下角度は
肉眼でみるとこれくらいの角度です。

これと同じことが水中でできれば、
沈むときは上図のように沈み、浮上するときは
対象に、(ゆるやかに斜め上に)進むので
航続距離は上図の2倍とれます。
さらに、もし、沈下/浮上をN回繰り返せるような
しくみにすれば、上図の(2×N)倍の航続距離がとれます。
こういう意味です↓ね。
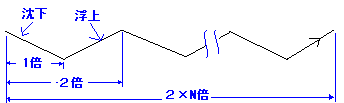
で、この図のぎざぎざが実際にはまっ平らに近いとしたら
これは充分に「大和スキャナ」に使えそうです。
沈下→浮上→沈下の折り返し点で、
重りを捨てる、浮き袋を捨てる、などのようなしくみを
繰り返しつかえば、大和スキャナが持っていくエネルギー源は、
サーボモーターや送受信機、ソナーを動かすに充分ならOK
推進力は重力と浮力でまかなえる(位置エネルギーの消化)
ということになり、より広範囲をスキャンできることになります。
>>>>>>>大和スキャナー(前座その4)につづく。
| 
