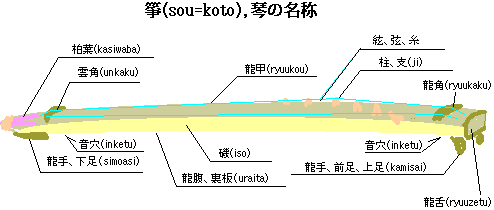
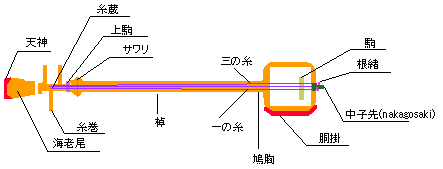
楽器の名称
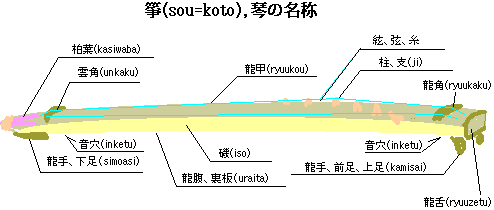 |
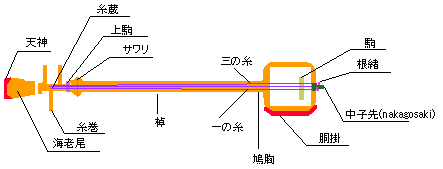 |
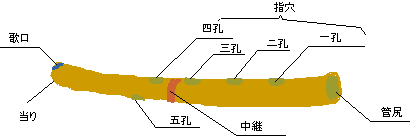 |
| 101 | 三曲 | 「曲」は、音楽あるいは、楽器の意味があるようです。”曲名”と言えば、音楽の題名ですし、”曲手”と言えば”楽器を弾く人”ですから、”三つの楽器”と言う意味に解釈すれば良いのではないでしょうか。 [現代三曲名鑑]によると徳川時代にも通用していたそうで、その頃の三つの楽器は、筝、三絃、胡弓ですが、明治以降は筝、三絃、尺八そして現在は、その延長上にある音楽形式を言うようです。 「俗曲評釈」(佐々醒雪:博文館)の記述によれば、八橋検校が作った組歌(箏曲)は全13曲で、当初は組分けされてはいなかったが後、新しい組歌が加えられ、表組・裏組にわけ、さらに中許(組)・奥許(組)等に分けられましたが、この区分の中には三曲という区分もありました。ここには秘曲とされる3曲がはいっていました。この三曲と言う区分名を語源とする説も有ります。ほかにも、八橋検校の組歌を表組7曲、裏組6曲に区分し、裏組を三曲ずつ区切りをしたのでこれを三曲の語源にしたとする説もあります。元々、三という数字ははよく使われる数字で、尺八音楽でも古伝曲の中、霧海じ、真虚鈴、虚空の三曲を古伝本曲あるいは古伝三曲と言う場合もあります。しかし、曲の数を指し示す意味と、音楽のジャンルを指す意味とでは随分かけ離れているようです。 元々、”三曲”と言う言葉自体に、特に決められた概念があったわけでは無かったようですが、地歌等の歴史的なことを考えてみると、三絃の伴奏で歌を唄っていた曲に、箏が加わる、また胡弓が加わって合奏曲にとなる、あるいは箏の伴奏で唄う曲に三絃の手付けをする、また、胡弓が加わると言ったことが行われるのですが、一般に洋楽と私たちが称している合奏形態とは大いに違い、各の楽器の曲は、合奏もできるが、また、独立した曲として各々の単独楽器で演奏してもいいように作られています。だから、前者(洋楽)のように、各楽器がバラバラでは曲にならないと言ったことにはなりません。このことから、合奏することは、三つの独立した曲でありながら、まとまった一つの合奏曲となるので、この合奏する行為を、三曲合奏と言ったのかもしれません。 明治以降、胡弓に代わって尺八が入りました。 現在はたんに箏(琴)と三絃(三味線)、それに尺八の三つの楽器を通称「三曲」合奏と言うが、場合によっては、ほかに十七絃箏が加わった場合や、逆にいずれかの楽器が欠けている場合、洋楽器が加わっている場合にも”三曲”と言い、日本の伝統楽器によるアンサンブル形を広く三曲と称しているようです。 戻る |
| 102 | 洋楽器との合奏が可能ですか | 当然出来ます。詳しく知りたい方は理論 を覗いてください。 戻る |
| 103 | 合奏の場合楽器の音あわせはどうすればよいのですか。 | 楽器の音を合わせる場合、尺八がある場合は尺八の寸法のよって音が違いますので、注意が必要です。尺八の筒音の「ロ」は一尺八寸の場合「D」音になります。一尺6寸の場合[E」音です。次に尺八みらの基準とする音と、琴の基準とする音同士を合わせます。これは譜面の指定によって合わせる箏になります。次に、その音を基準に、音階に「支」を並べます。(たとえば「平調子」とか「雲井調子」といった風にです。)「みそたねくん」オリジナル早見表です。琴・尺八・三絃早見表を使ってください。 戻る |
| 104 | 伝統芸能とはどのようなものですか | 伝統と言う文字は、広辞苑などによれば、「むかしからうけ伝えてきた、有形無形の風習、しきたり傾向様式」と、なっています。そして、「芸能」は、大衆的娯楽の総称であるわけです。 さて、ここで重要なのは、”むかし”とはいったいいつ頃を指すのかと言うことであります。 日本むかしと言えば、まさか縄文式とか弥生式土器時代からの”伝統芸能”なんて言う物はまず無いでしょう。 であるとすれば、いずれかずっと後期(近世に近づいて)に自然発生的にあるいは誰かの考案が大衆に支持され根付いて今日に受け継がれてきた物であると考えられます。 では、いったいいつ頃の物であれば伝統的と言えるのでしょうか。 これは、かなりデリケートな問題で結構、新しい時代の物であっても伝統と呼んでいる物が結構あるようです。 一般的には今日の伝統芸能は江戸時代前後に発生した物が多いようです。 最初は普遍的な物から、ある、特別な才能をもった人物などによって飛躍的に変化を遂げ一般から差別化された芸能が生まれ、大衆に支持されつつ年月を経る事によって伝統芸能となるわけであると思います。 伝統芸能もどこかで創造されるのであります。 そして、これらは、当然、国によって保護されたり、ある組織によって守られたり、あるいは個人から個人へと受け継がれて継続されるのです。 しかし、これらがいったん途絶えてしまい、中断の時期があって、後に資料などによって再現されてものが伝統といえるなら、むかしの物を模倣すればすべて伝統と言えることになってしまいます。が、そうはならないでしょう。 しかし、これが継続されて後生に伝わったなら、これも新たな伝統となるはずです。 ここから、伝統芸能は創造期があり、受け入れる側である大衆に、十分な時の長さを感じさせる歳月を経て、かつ、大衆に支持されるに足りる時代性を持っているもの、であると言えます。 伝統を単に受け継ぐだけではすぐに自然消滅してしまうわけであります。やはり、大衆に支持されるべき時代性を取り入れた生きた芸能でなくては継承できないわけであります。 そして、いま、創造している人は次世代の伝統を作り出している人でもあるわけです。 戻る |
| 105 | 家元とは | 広辞苑によれば、その流祖の正統を伝える地位にある家人、宗家とある。 言葉の解釈は兎に角として現実的には、お師匠さんに教えを受け、ある句切り(たとえば修歳月とか、一定の習熟度により)免状を交付するシステムである。 当然、そこでは免除料として、お金の収受が行われるわけである。宗家への収入として、あるいは一部が師匠への配分がなされる。 さて、いかにも日本的なシステムのようで、何か古くさい封建制度の代表格のような、悪玉のイメージを持たれている人も多いと思う。 しかし、よく考えてみると、なにも日本だけの特殊な形態ではないことがわかる。 今日の資本主義社会においては、重要な企業あるいは個人の権利を守るシステムとまるっきり同じであることがわかる。 それは、”物事”の創始者の権利を保護する、特許、意匠と同じで、創始想像した本人はもとより、その企業、一族が当然の権利として占有を継続することができるのが普通でありまた法律でも保護されているのである。 また別な言い方をすれば、ある種の商標と考えれば、それを無断で使うことは禁じられているのは誰もが周知の事実である。当然のことながら、家元の発行する看板を無断で使うことができないのはこれからすれば論を待つまでもない。 さらに言えば、近代的に言えば、コンビニのように看板を借り、ロイヤリティを払うように物質と、芸という無形の違いはあれ何ら変わらない商取引の一変種なのである。 日本の芸事は、お師匠さんが教授の代償に月謝を受け取り、芸を教え、弟子がある一定の習熟度に達したとき家元に免状を申請する。 学校であれば、卒業するときに一回卒業証書という免状を戴くが、芸事の場合は幾度も段階を追って免状をもらうことになる。当然、そのときに免状料を払うことになるが、一回がいいのか何回も払うのがいいかは一概にはどちらが言えない。 当然、学校の卒業証書がタダだなんて思いこんでいる人はいないだろうと思うが、当然、卒業までの間に支払う授業料には、卒業証書どころか先生の給料、学校という組織維持のための費用、さらにはオーナ−の利益も当然含んだものを支払っているのであるが、家元制の場合は、月謝は先生個人の収入分のみしか支払っていないのであるから、当然、どこかで、組織の維持費や家元というオーナーに利益分を支払をなければならない。 いずれにしても、邦楽組織が国民に義務を負わせているものではないので、組織の一員になるならないは個人の自由であるから、家元制の善悪は軽々に述べがたい。 最終結論は時が自然に回答を出すからである。 戻る |
| 201 | 筝と琴の違い | 琴は、弦楽器の総称であり、”筝”は、柱(駒/ブリッジ)を動かすことが出来るものを言います。 戻る |
| 301 | 材質 | 普通は竹です。日本の三大竹(孟宗、破竹、真竹)のうちの真竹を使います。 現代では、楓や、樹脂の廉価なものが作られています。ほかにもいろいろあるようですが一般的では有りません。 戻る |
| 302 | 長さ | 長さは通常1尺8寸の長さの尺八を指していまして、この場合54.5センチです。このほかにも、三曲では、1尺6寸の長さの物をよく使います。1尺は、30.3センチですから掛け算すれば長さが分かります。 このほか、民謡は、1尺3寸ぐらいから2尺4、5寸の長さのものを使います。一般には、1寸短くなれば半音高くなりますが、長くなれば少し長めに補正しなければなりません。 戻る |
| 303 | 流派による違い | 一番の異いは、歌口の部分です。琴古流は三角形、都山は三日月、明暗は、弧形の三種類が主流です。 戻る |
| 304 | 歌口の材質は何で出来ていますか | 主として黒い色をした水牛の角です。白い色の象牙も有りますが、今は象牙の使用が禁止されています。古くは竹の表皮をはめ込んだのも有ります。 戻る |
| 305 | 尺八がいつ伝わったか | ”尺八”は、正倉院にも納められているところから、奈良時代以前に有ったと考えれれますが、今のような形のものは、江戸時代に入ってからではないでしょうか。戻る |
| 306 | 虚無僧は誰でもできるのか | 結論から言えば誰がしてもよいでしょう。虚無僧は明治4年の普化宗廃止までは本則を受けた者でなければできませんでした。しかし、普化宗が政府によって解散を命じられ以降、普化宗は存在しなくなりました。 現在は、同好の人などが集まり、普化尺八音楽を伝承しています。 代表的な物は、東福寺内(京都)に再興された明暗寺、興国寺(和歌山県由良町)、虚無僧研究会(東京)などがあります。 いづれにしても、尺八を吹けなくては話になりません。と言うことで、尺八の先生に就いて習うことになるのですがこのことは、どこかで普化宗につながっていることになるのです。 だから、尺八を吹く人にとっては、虚無僧とはまるっきり、無縁と言うことではないのです。 戻る |
参考資料
| 日本音楽の歴史と鑑賞 | 星 旭 | 音楽の友社 |
| 邦楽鑑賞入門 | 吉川英史 | 創元社 |
| 筝曲と地歌 | 吉川英史、林兼三、岸辺成雄、平野健次、星旭、伊藤隆太 | 東洋音楽学会 |
| 現代三曲名鑑 | 藤田俊一 | 日本音楽社 |
| 名曲解題 | 藤田斗南 | 上方郷土芸術保存会・昭和34年刊 |