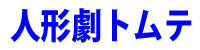
パネルシアター 紙芝居 絵本 絵話 のぞきからくり 世は歌につれ スタジオ (各種通信講座、SEO対策) ブログ「人形劇のお弁当」 リンク集 |
布絵本
ぼくのカメ君
内容:
手作りの絵本というものは、とても暖かみのあるものです。その中でも布を利用した人形仕立ての立体絵本は、盲人用の絵本としては非常に重要で貴重なものでもあります。版を重ねるにも、手作りの上に手作りという形でしかできません。ただ、その絵本は触れてこそその持ち味が活かされるものですから、痛みも早く修理などに追われることになります。 修理には最初に使った材料をちゃんと整理して保管しておかないと、同じ物を手に入れるということが困難になります。そういう大変なこともありますが、一番の課題はその絵本を制作する人が少ないということです。 お年寄りの中には器用な方がたくさんおられて、趣味でいろんな作品を作られています。その作品の展示会を開いたり、感謝の気持ちで人にさしあげたりと喜ばれることもしばしばです。しかし、一方ではすてきな作品が引き出しや押入れの奥で眠ってしまい、日が当たらずじまいということもあります。ひょっとするとそんな作品たちが、立体絵本として生まれ変われる日をじっと待ち望んでいるかもしれません。 立体絵本の制作する方は、小さな人形を作るという細かな作業のため、手先が器用な方が向いています。また、主人公がウサギだと、そのウサギの肌触りのする生地を探すという根気さも必要です。点字もレイアウトしますので、点字にもある程度の理解がないとこの絵本ができないことになります。しかし、多くは自分の得意とする部分を受け持つことになりますが、登場人物の服をこしらえているうちに裁縫が得意になっていくこともあります。点字も最初は分からなくても、やっているうちに次第に理解が深くなるということもあります。 この絵本は一人で時間をかけて作るよりも、むしろグループでの共同作業で作る方がいいでしょう。たくさんの人の手が加わり生れた一冊の絵本には、たくさんの人の思いや願いが詰まります。また、共同作業だと制作者たちが話し合いながら制作を進めることになり、自然に人と人との交わりが多くなり、孤独からもどんどん遠ざかることにもなります。役立つ絵本であるなら、なおさらいろんな工夫やアイディアが生れてくるものです。そこには若い人にはない経験というものから生れてくるものもあるでしょう。子どもの頃の思いでが主人公の表現を豊かにしたり、昔の建築物や風景の立体模型を作ったりと、みんなの力がひとつになり一冊の絵本が仕上がります。 絵本に限らず子ども達がお話しに出会うということは、そのお話の中で子ども達が疑似体験するということです。生きる希望をなくして、自殺することは悲しいことです。絵本には、生きる道標が隠されています。その道標のひとつひとつを発見していくことが、幼い子の生きる力になっていきます。その道標を立体絵本の中に表現できたらどんなに素晴らしいことでしょう。そうなれば、立体絵本は単に目の見えない子ども達だけのものではなく、目の見える子どもから大人たちまでも巻き込んでいきます。また、立体絵本の制作で活躍しているお年寄りがいるということは、他のお年寄りへの何かの励みにもなります。 立体絵本は、目の見える親が目の見えない我子に読んであげてもいいでしょうし、目の見えない親が点字の部分を読みながら、目の見える我子に読み聞かしてもいいでしょう。しかし、もともと立体的になっている絵本というのは、それだけで見る側を楽しくします。そこに点字がついていれば、それについて親子で話すこともあるでしょうし、町で見かける点字ブロックの重要性や福祉に対する関心を持つきっかけにもなったりします。 さて、どこかに心のバリアフリーを目指して、特技を活かそうという方はいないでしょうか?特技はなくても情熱を持った方や新しい人生の道標を立ててくれる方はいないでしょう?ただ今、立体絵本を作っていいただける方を募集しています。
なぜ「おやすみ、ロジャー 魔法のぐっすり絵本」を読めば眠くなるかというと、心理学・言語学研究者の著者(カール=ヨハン・エリーン)が、「子どもがなぜ寝たくない気持ちになるのか」を徹底的に考慮しています。自然に眠くなるよう「ここを強調して読み、ここであくびするように」などの細やかな指示が絵本の中に入っています。従来のいわゆる「おやすみ絵本」とは違ったコンセプトで、理論にもとづきお子さんをリラックスさせます。これと布絵本の質感が合い交われば、向かうところ敵なしです。 時代をつなぐ街(東京):
|