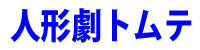kamishibai 紙芝居 kamishibai
紙芝居の必需品

舞台
紙芝居舞台
一般的な舞台の仕様(画面サイズ:34.6×24.7cm)
扉:扉を開くと舞台の袖になる。
緞帳:舞台と観客席とを仕切る垂れ幕、または上手下手に開く幕。
設置台:舞台をを設置する演台。会議室のテーブルを利用して、足元を隠す幕をする。
拍子木(ひょうしぎ)
紙芝居では、客寄せに拍子木というのが一般的ですが、鉦や太鼓、鈴などを愛用している人もいます。ちなみに、クラベスも木のいい音を響かせ効果的です。
 鉦というと、昔見たのはハンドベルのようなものです。今ならチャイムがなると思いますが、学校で授業の始まりの合図に使ったり、休憩時間の終わりを告げたりしていました。ハンドベルというと、クリスマスのときに教会でハンドベル演奏をしたり、歳末の抽選くじのときに使ったりしますが、それとは違います。もっと大きくて重量感があるものでした。今はそのような鉦を売っているのを見かけたことがありません。骨董品店にでも行けば見つかるかもしれません。鉦というと、祭りのときの囃子に使ったりします。紙芝居では、客寄せというより囃し立てる効果音として使うことが多いようです。
鉦というと、昔見たのはハンドベルのようなものです。今ならチャイムがなると思いますが、学校で授業の始まりの合図に使ったり、休憩時間の終わりを告げたりしていました。ハンドベルというと、クリスマスのときに教会でハンドベル演奏をしたり、歳末の抽選くじのときに使ったりしますが、それとは違います。もっと大きくて重量感があるものでした。今はそのような鉦を売っているのを見かけたことがありません。骨董品店にでも行けば見つかるかもしれません。鉦というと、祭りのときの囃子に使ったりします。紙芝居では、客寄せというより囃し立てる効果音として使うことが多いようです。
参考:当り鉦チャンチキとは
紙芝居では、太鼓がひとつあると音の高低や強弱をつけるだけでも、その場面を表現する効果として絶大です。より具体的な音に近づこうとしたり、スタッフが多いときには効果音が収録されている
CD:とく得BOX 効果音が役立ちます。
擬音楽器
擬音楽器とは、波の音、風の音、鳥や虫の音などの音を表現するための楽器です。紙芝居、その他人形劇などでもワンポイントとして効果が期待できます。オノマトペと言われる擬声語や擬音語と検討して使うことが肝心です。
 カラス笛
カラス笛
吹く口から吹くとカァー、カァーとカラスの鳴き声を出すことが出来ます。簡単に音が鳴りますので、お子様への玩具、人形劇、紙芝居、演劇などの効果音、音遊びになど様々な用途に使えます。
日本製
全長:約11cm
ブランド: 民族楽器コイズミ
 赤ちゃん笛
赤ちゃん笛
手で押さえながら吹くと、オギャァ〜と赤ちゃんの泣き声のような音が出せます。吹き方を変えればコケッコッコーと鶏のような音も出せます。簡単に音が鳴りますので、お子様への玩具、人形劇、紙芝居、演劇などの効果音、音遊びになど様々な用途に使えます。
日本製
全長:約14cm
 鈴虫笛
鈴虫笛
二つの笛を一度に吹けば共鳴しあってリーンリーンと鈴虫の音色に聞こえます。小刻みに吹けばコオロギの音色にもなります。簡単に音が鳴りますので、お子様への玩具、人形劇、紙芝居、パネルシアター、演劇などの効果音、音遊びになど様々な用途に使えます。
日本製
全長:約13cm
 レインスティック
レインスティック
雨の効果音が楽しめる楽器が「レインスティック」です。レインスティックの起源はアフリカと言われ、中南米まで広く伝わったとされる楽器です。古来、先住民が雨乞いの儀式に使い、現在も南米チリのカトカマ砂漠では雨乞いの儀式の道具として使われています。
乾燥させた筒状のサボテンの内側に多くの突起(トゲ)が並んでおり、揺すると種が当たってザザーッ、ザザーッと響きます。静かに聞いていると本当に心が癒されるような感じがします。
南米チリ製、サイズ: 50cm
上に紹介されていない猫笛、
牛角笛、
フィンガーシンバル、
擬音笛セットなどもございます。詳しくは擬音楽器をご覧ください。
 オノマトペ擬音・擬態語をたのしむ
オノマトペ擬音・擬態語をたのしむ
田守 育啓 (著)
他の言葉では代えがたい、表現力豊かなオノマトペ。感覚的に使われるから自由に創り出せそうに見えながら、意外にきっちりしたルールがあるところが面白い。音と意味が響き合う、不思議な世界をのぞいてみよう。
単行本: 178ページ
出版社: 岩波書店 (2002/9/10)
|