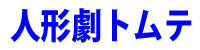
パネルシアター 紙芝居 絵本 絵話 のぞきからくり 世は歌につれ スタジオ (各種通信講座、SEO対策) ブログ「人形劇のお弁当」 リンク集 |
 パネルシアター
パネルシアター
ばけもの寺旅のお坊さんが、夜更けにたどり着いたのは、誰ももう住まなくなった、壁は剥がれ落ち草ぼうぼうの荒れ果てた古寺でした。そんな古寺でも夜露がしのげればと宿をとろうとしますが、古寺の中には、傘、提灯、下駄の三匹のお化けたちが潜んでいました。お化けたちは、謎解きを迫って旅人を寝かしてくれません。旅人が困るのを見るのが、唯一の楽しみのお化けたちです。 「一本足の骨と皮。わたしはだあれ?」「・・破れ唐傘のお化け」
お化けたちの難問に答えているうちに、夜が明けてしまいます。そして、お坊さんは、また長い修行の旅に出るというお話です。実演には効果音を使うと、ぐっと引き締まってきます。 パネルシアター「ばけもの寺」 時代遅れの提灯お化け 夏の風物詩 小さい子たちには、唐傘、下駄、提灯などは馴染みがないかもしれません。私の小さいころは、時代劇のように、実際生活で提灯を使っていました。月明かりで夜道もずいぶん明るかったので、月が出ていないときに使っていました。提灯のような小さな灯りでも、結構道を明るく照らしたものです。そのうち、懐中電灯ができてそちらを使うようになりました。その頃、使った懐中電灯は、四角い箱のようなものの前に電灯がついていました。銀色をしていたので、全部金属でできていたように思います。その後、筒のような懐中電灯ができましたが、それでも金属だったと記憶しています。今のようなプラスチックになったのは、ずっと後からです。 月がとても明るかったのと同じように、天の川も一年を通じてみることができました。宮沢賢治が見ていた夜空と同じ夜空をそのころは見ていました。最近は、空気が汚れていて、大阪にいる限り天の川を見ることはもうありません。星も数えることができます。数えることのできない無数の星たちは、もうどこか御伽の世界のことのようです。 この『ばけもの寺』では修行僧をなぞ掛けで困らせますが、まんが日本昔ばなしの『古寺の化けもの』に登場する化けものは、床下から這い出てきて旅のお坊さんを生きて帰しません。
|