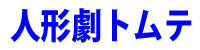
パネルシアター 紙芝居 絵本 絵話 のぞきからくり 世は歌につれ スタジオ (各種通信講座、SEO対策) ブログ「人形劇のお弁当」 リンク集 |
人形劇の練習めんどくさくても手順を踏んだ練習がいちばんの近道[本読み]先に台本を渡されれば、個人的下読みをしておき本読みのときの準備をしておきます。スタッフが集まり、演出かなり脚本家なりが代表で台本を読みます。この本読みのとき、注意事項や訂正があるかもしれません。下読みしたときの疑問など聞いておきます。この本読みでみんなが、人形劇公演のスタートラインに立つことになります。 本読みで自分がどんな役をしたいか、どんな役が適切なのか、劇にはどんなものが必要なのかなど色々わかってきます。劇の意図することやまだわからなかったことがわかります。最初自分がやりたかった役が変るかもしれません。本読みが済めば、役を決めます。役が決まれば、その配役で台詞を言って読み合わせがはじまります。
[読み合わせ]読み合わせがはじまりだすと、脚本家はもともとの台本で気がつかなかった不備が見えてきて、いきなり訂正が出したりすることがあります。また、自分の役で忘れてはならない大切なことがわかることが出てきたりします。チェックや朱入れが大事になってきます。台本への書き込みが多くなりどんどん汚れていきます。汚い台本になっていくに従い、その台本がその劇の真の台本になって行きます。 たとえば、人形劇「わにくん、ははは」では痛い歯を抜いてあげるという友だち思いの話です。それでは特に感動も面白くもありません。感動とは、心に動きがあることです。情緒の起伏があって、楽しい劇に仕上がります。あらすじだけでは、感情の微妙な振れは起こりません。そこで脚本に工夫を入れます。ワニだから獰猛で大きな口で何でも食いちぎってしまいます。おなかがすいたと言っているのですから、もしかして友達を食べてしまうかもしれない。だけど友だちなんだからそんなひどいことはしないはずと、観客は思っています。でも口の中に誘い込んで食べるかもとふと思ってしまいます。その観客の揺れる気持ちを意図して作られているんだということを知っておきます。そうすると台詞の言い方にも意味を持たせられます。
このように人形劇の中には、観客に向けて何らかのメッセージのようなものが隠されています。それを子どもたちは感じて情緒が培われます。こどもにとっては親しみやすい人形劇が心の成長に役立ちます。でもそういう堅苦しいことを考えずとも、おもしろい人形劇をと考えを持てやっていれば、その面白さが観客に伝わっていきます。 読み合わせは、はじめのうち毎回練習のはじめにすればいいでしょう。人形が完成していてもいきなり人形を操作してやるより、行きつ戻りつしながらやる方が練習になります。人形を持つと動かすことに神経が行ってしまって、しゃべることがおろそかになりますから。特に声色を使う必要はありません。自分の役作りをしておけば、自然とその役の声になっていきます。
[立稽古]台詞を覚えていなければ、台本を横に置いて、片手で操作して人形を動かさなければなりません。それでは自分の人形がどんな動きをしているか分からなくなります。台本は読み合わせのとき利用して、人形を持っての立稽古では原則台本は持ちません。自分の台詞だけ覚えていたのでは、人形の動きによって台詞のタイミングが変わるので、相手役の台詞も覚えておきます。 読み合わせのときは、セリフは台詞で構いませんが、立稽古では科白(せりふ)になります。科はしぐさ、白は言葉ですから。ですから台詞を覚えた人とそうでない人には、立稽古では明らかな差が出ます。覚えた人の人形の動きと台詞は、一体化していくのがよくわかります。 小道具がまだ製作中なら、あるつもりでやることも大切です。イメージ作りに役立ちます。見落としていたものを発見することがあります。人形劇では、一般的に演技者よりも人形の方が小さい。だけど、人形と同じくらい蹴込の中の人間も動きをします。小手先だけで人形を動かしても、人形からにじみ出るような演技表現は出てきません。人形と一体化した動きをすると大変疲れるものです。
[通し稽古]小道具などが出来て本場のような条件がそろうと、劇のはじめから最後まで通しで練習をします。どれだけ時間がかかるか、人形や道具をどこに配すればいいのか、どの場面で誰がどこにいるかなど通し稽古をするとわかってきます。どの場面が練習不足かも分かってきます。通しで練習すると時間がかかるので、そういう場面は何度か返して稽古をします。返し稽古をすることによって集中的な練習ができます。 通し稽古では全員持ち場につく必要はありません。例えば、あるときは照明係には観客になってもらって、観客目線で劇のアドバイスをします。メンバーが少ないと演出家としての役割もいないかもしれません。全員で人形劇を作ると言うことになります。
[総稽古]本番と同様の感じで稽古をします。失敗しても進行を止めることなく最後までやり通します。一気に緊張が増す稽古になります。今までどんな練習をしてきたのか試される練習でもあります。どこかで失敗をしてそれをカバーできるかどうかも分かります。誰一人として休んでいないということがわかり、役割分担という本当の意味を知ることになります。
|