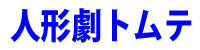
パネルシアター 紙芝居 絵本 絵話 のぞきからくり 世は歌につれ スタジオ (各種通信講座、SEO対策) ブログ「人形劇のお弁当」 リンク集 |
パネルシアターの演じ方演じ方のポイント
文化的なことしているようで、実はスポーツ的なことをしています。人形劇と人形劇の合間にパネルシアターをすることがあります。人形劇を今でも中腰でやっている人が多くいます。「さあ、次はパネルシアターだ!」と立ち上がったとたん、ぎっくり腰で腰を痛めることもあります。司会に立っているだけでも、サポーターがいる人もいます。それがないとすぐ腰が曲がってきて、客席からはかっこよく見えません。すっくと立っている姿は客席からは見栄えよく映ります。 客席ではどんな楽しいお話がはじまるのかと、みんながわくわくしています。司会者が恐そうな顔で立っていたら、そのわくわくは半減します。笑顔で立っているのが、パネルシアターの演技者も基本姿勢は同じです。演技者自信が司会をかねて進めるのであれば、最初から立ち位置にいても、舞台前にいてもかまいません。司会のときは、左右に動く動作はできるだけしません。前後なら多少はかまいませんが、左右では観客の視線が定まらなくなります。
絵人形に使われている塗料と照明の関係で、絵が光る場合があります。事前に絵人形を配置して、客席から自分の目で確かめることです。しいては、それが、客席からどのように観られているかのイメージをつかむのにも役立ちます。また、本番の前にエアコンの風に気がついて、その対策に苦慮しないですむかもしれません。特にブラックパネルシアターや透視パネルシアターは、会場でのリハーサルが重要な部分を占めます。 複数で演じるときは、役割分担を決めておくといいでしょう。役割分担というと、そのパートだけ責任を持てばいいという考えが浮かびますが、これは間違いです。そのパートを仮に受け持つだけであって、責任は全てに及びます。本番では何が起こるかわかりません。そのフォローをできるのは、あなただけかもしれません。他の人の役割が何なのか知っておかないと、フォローのできない役割分担には意味がなくなります。 複数の人で複数の演目を公演するとき、お話がぷつんぷつん切れてしまうことがあります。みんなで演目の順番を考えて、構成したはずなのですが、みんなばらばらになってしまうことがあります。それは前後の演目に関係なく、次の演目が上演されるからです。演目と演目の間に司会者を入れるようにすると、つながりがでてきます。また、演技者が上演のはじめや最後に、前後の演目について少し触れると、つながりができて、全体としてみんなで考えた構成の通りにお話が進んでいきます。 実際の絵人形の出し入れの練習は言うに及ばず、イメージトレーニングも重要です。これは、舞台を出さなくても、パネルシアターを出さなくてもいいので、時間さえあればどこでもできます。イメージを追って台本を書いていくのと同じよう要領です。台本が書ける人であれば、この練習はそう難しいものではないと思います。本番で演じている自分をイメージしていくと、どこで詰まるかすぐわかります。そういうところが、当日失敗する可能性がでてくるところです。修正できないときは、その部分だけ実際やってみると、問題点が見つかります。 パネルシアターに魅了されて、実際触ってみたいこどもやおとな達がたくさんいます。終演後、根掘り葉掘り質問攻めにあうことがあります。何度か公演していると、だんだんそういうことはわかってくることです。事前に体験コーナー用の絵人形を用意しておきましょう。その間に本番で使った絵人形を片付けましょう。体験用は、もう使わなくなった絵人形とか、万が一折れたり破けたり、なくしてもかまわないものを用意しておきます。
|