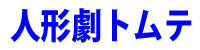
パネルシアター 紙芝居 絵本 絵話 のぞきからくり 世は歌につれ スタジオ (各種通信講座、SEO対策) ブログ「人形劇のお弁当」 リンク集 |
人形劇の演技上下の出入りは袖幕の幅を十分利用して登場したり退場したりします。各席から見えている舞台の大きさだけを考えていると、人形が地面から出てきたり土にもぐりこんだりすることになります。観客に場面の狭さを感じさせます。メンバーが沢山いれば観客になってもらい客席から見てもらいます。椅子に座るか床に座るかで見切れ線が変わり人形の高さも違ってきます。小返しを入れながら立ち稽古をします。
例えば『わにくん、ははは』では、わにのしっぽと口は演じる人が違います。二人でみんなとは別個に練習すると集中できます。小鳥とわにの口、かえると浮き草、波しぶきとカエル、わにと水しぶきというように組み合わせによって練習します。まだ完成されていなくても、一通り演技ができれば、練習の最後に通しでやってみます。途中で失敗してもいいので、中断することなく最後まで演じます。本番は中断できないのですから、スタッフのみんなが人形劇の完成をイメージできるようにやります。どこがネックなのかもわかり、練習の仕方も変わってきます。
普通人形劇俳優が大きく人形は小さくなりますが、客席に見えないからと言って蹴込の中で小手先の動きをしません。人形が右を向けば演技者も右を向きます。そうすることによって人形と演技者が一体化してきます。人形に気持ちを伝えやすくなります。台詞の調子も自然となっていきます。人形と台詞がばらばらなることがあります。多くは台詞を覚えていないからです。台詞を覚えると一気に人形の演技が上達します。役作りを進めていれば、さらに台詞にも演技にも自信が出てきます。恥ずかしいと思っているうちは、人形にもその恥ずかしさが伝わり、役としての動きが出てきません。
人形の動きも大事ですが、やっている人間の気持ちで人形が左右されます。自分の役の人形を自分なりに設定します。ワニの年齢はいくつか、すきなたべものは何か、今日何時に起きたのか、お父さんやお母さんはいるのか、どこで生まれたのかなど自分で仮の設定をしておくだけで劇の中の架空のわにが、実態のあるわにとして自分の中で消化されて行きます。架空であるにもかかわらず、舞台の中で生き生きしてきます。それが役作りです。 雲を動かすとき客観的に見た動きをしてしまいがちですが、自分が雲になったならどんな動きをするだろうかと考えて動かすと、人には真似できないその人自信の雲になります。会場に暗幕があれば練習も暗幕をして、できるだけ本番の会場の環境にあせてすることが大切です。本番と非常に近い状態で総稽古をします。誰かはじめに司会に出るのであれば、そこからはじめ最後の挨拶まで通しで練習します。台詞を覚えたり人形を動かしたりすることだけが練習ではありません。メンバーがどこで何をしているのか、人の配置も頭に入れておきます。本番では余裕を持って準備し、簡単なりリハーサルをしておくだけでも緊張のしすぎを緩和できます。 公演が複数回あるときは、必ず反省会を設けましょう。問題点がなくてもやります。1回目うまく出来ると安心するものです。そこに落とし穴があって、2回目は失敗することが多いものです。舞台は観客が違うように同じ人形劇をすることは難しく、次はああしようこうしようと考えておくと、新しい緊張感で公演できます。その緊張感が、より良い舞台になって行きます。 人形劇の演技練習 人形使いとは 人形劇の役作り 人形劇の人形目線
|