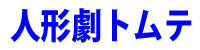
パネルシアター 紙芝居 絵本 絵話 のぞきからくり 世は歌につれ スタジオ (各種通信講座、SEO対策) ブログ「人形劇のお弁当」 リンク集 |
台詞の練習人形劇の練習は読み合わせのところから始まります。自分のせりふだけ覚えればいいと思っている人がいますが、自分が関連している部分の台詞は全部覚えます。せりふは掛け合いになりますから、相手のせりふも覚えていないと会話が成立しません。万が一のときにも本番では切り抜けられます。たとえば、本番で相手が台詞を忘れたとき、アドリブで切り抜けることが出来ます。最悪誰かが病気や怪我で役ができないとき代役が出来ます。練習のときでも同じことが言えます。 練習していると声が小さいと言われることがあります。地声が小さいのであれば、大きな声が出るように発声練習すればいいでしょう。発声以前に口の開きが小さいことがあります。口を大きく開いて「お綾、親にお謝り、お綾八百屋にお謝りとお言い」と3回ぐらい続けて早口ではっきり言います。自然と口が大きくなり大きな声が出るになります。ゆっくり伸ばすように言うと、横隔膜が鍛えられて大きな声が出るようになります。また、マイクに頼ろうとすると小さくなり、マイクがなくても自分の声よ客席に届けというように意識するだけで声の張りが違ってきます。 台詞の終わりの方が聞き取りにくいと言われたりすることがあります。「やあ今日はいい天気だ。でもおなかもすいたなあ」を言うときには、練習のとき言葉の最後を強く言うに意識をするようにして言います。そうすると尻切れトンボのように終わりの方が消えてしまうこともなくなってきます。文章にするとわかりづらいですが、こんな感じです。「やあ今日はいい天気だ。でもおなかもすいたなあ」それと気持ちとしては、点から点、丸から丸までを気持ちを切らずに言います。長い台詞は息を継がないといけませんが、息継ぎばかりしていると気持ちが切れやすくなります。気持ちを切らずに言うと間があいても台詞がつながっていきます。 歯切れが悪いと言うこともあります。 滑舌をよくするには、早口言葉が入っている『外郎売(ういろううり)』 『こんきょうじ』などがおすすめです。パネルシアター「じゅげむじゅげむ」のページにも関連記事があります。 ここでは、発声練習として北原白秋の「五十音」を紹介します。あいうえおの歌と呼ばれ親しまれています。 役立つ発声練習よりTEXT動画:
音声動画:
柿の木栗の木 かきくけこ きつつきコツコツ 枯れケヤキ ささげに巣をかけ さしすせそ その魚 浅瀬で刺しました 立ちましょラッパで たちつてと トテトテ立ったと 飛び立った なめくじノロノロ なにぬねの 納戸にぬめって 何ねばる 鳩ぽっぽホロホロ はひふへほ 日向のお部屋にゃ 笛を吹く まいまいねじ巻き まみむめも 梅の実落ちても 見もしまい 焼き栗 ゆで栗 やいゆえよ やまたに火のつく 宵の家 雷鳥は 寒かろ らりるれろ れんげが咲いたら るりの鳥 わいわい わっしょい わいうえを 植木屋井戸がえ お祭りだ 参考:滑舌をよくする
上の50音の大切なところは早口でいうというものではありません。無声音や鼻濁音を理解してきれいな日本語で、要するに聞き取りやすい台詞でお話できるかというところにあります。 無声音とは文字としてはきちっとあるのに、声にしてちゃんと発せられない音です。英語にはよくあるのに日本語ではあまり意識されていません。意識しなくても普段使っているので問題になりません。しかし、台詞を言うときにそのままの文字を発しようと努力するので、ややもするとギクシャクした日本語になります。たとえば「きつつきコツコツ」です「キツツキは4文字です。実際にはもっと短縮されて聞こえます。文字は「KITUTUKI」でも発音すると「kitutuki」になり、文字も短くなった感じです。二つ目の「つ」が消えた感じになります。「コツコツ」も無声音で「コ・ツ・コ・ツ」とは発音しません。何とも文字を音にするのは難しい。 鼻濁音とは鼻にかかる発声です。濁って聞こえると言うことで鼻濁音です。「焼き栗ゆで栗」では「ぐ」が鼻に抜けます。鼻をつまんで言うと抜けませんので、言いづらくなります。濁っているのできれいでない、汚いと言う表現をしますが、方言によってはごく自然な発声ということもあります。むしろその方言がきれいと言うことにもなります。アナウンサーなどは無声音・鼻濁音を勉強しますから、きれい汚いは別にして聞き取りやすいこと言葉になります。台詞も同じです。 「こんにちは、かえるさん。何してるんだい」を気にされる人がいます。「何をしているのだい」としたいかもしれません。文語体・口語体の違いやい抜き言葉であったりします。言葉は生きているとよく言われます。ら抜き言葉であったとしても、その舞台で生きた言葉であることが優先します。「わにさんは水にもぐったり、自由に泳げて楽しそう」で「自由」「じゆう」言うより長音化させて「じゆー」と言った方が、自然に聞こえるかもしれません。その公演地の言葉を使った方が説得力があることもあたりして、一概に間違っているとも正しいとも言えません。その他アクセントばかりに気を取られて、その人形劇の意図をおざなりにしないことです。
|