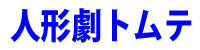
パネルシアター 紙芝居 絵本 絵話 のぞきからくり 世は歌につれ スタジオ (各種通信講座、SEO対策) ブログ「人形劇のお弁当」 リンク集 |
棒使いの人形の作り方棒使い人形は、棒使いとも、棒遣いとも呼ばれている人形です。「使う」は、道具などを使う。お金を使う。人を使う。というように広く一般的に「使う」を使います。「遣う」は、何か工夫や意を尽くして、それを活かすときなどに使います。どちらかというと、「遣う」は、気持ちをこめて遣う時に使います。こだわらなければ、どちらを使っても正解ですから、好きなほうを使ってください。 人形を動かすときに、直接手からその動きが伝わる人形、糸を張ることによって動く人形などいろいろあります。明確な境界線はなく、その人形の主たる動きが棒でなされていれば、棒使い人形です。よく見かけるのが、人形の体から頭頂へと棒が串刺しになり、腕がピアノ線で動かされるというものです。主たる体の動きは棒であり、腕の動きもピアノ線という棒で動かされるものです。ピアノ線は使わず、棒だけで動かすこともあります。串のように棒が通されていますから、串人形とも言います。串が人形の体を通らず、頭部に固定されているものもあります。提灯のようにぶらぶらさせて、その動きを人形の動きに転化させて動かすこともあります。
人形劇「おか釣り」の人形たちは、すべて棒使い人形です。手首にピアノ線(差し金)がありませんから、自由に手が動くわけではありません。下から糸を引いて動かす仕組みになっています。糸で引く場合、その糸は観客にほとんど気づかれることはありません。ただ、動きに制限があるので、決まった動きしかできません。手を合わせるとか、手を上げるとか、手を広げるとか、体の動作と組み合わせて単調な動きに幅を持たせます。もっとも、あっちにこっちに手を動かせば表現できると思いがちですが、あまり動かなくても表現は出来るのです。 なお、人形たちの頭(かしら)は、すべて石膏で型取った張り子(張子人形の作り方)です。大工の弁さんは、すべて木質の粘土で出来たいます。
写真は、「リトルサリナ」という名前の棒使い人形です。両手首のところにピアノ線がついています。それを右手で操作します。人形自体は、左手に乗っていて、左手の親指と人差し指で支えて、かつ、首を上下左右に動かす仕掛けを作っています。左の親指と人差し指が忙しいのですが、慣れないと使っていない指(左手の中指・薬指・小指)が助けようとします。助けようと中指・薬指・小指が曲がってきます。親指と人差し指思いの指たちです。中指・薬指・小指を使えば、もっと楽に動かせるのでしょうが、使わないということで、この人形を表現しているのです。効率ばかり考えていると、新しい表現は生まれてこないです。人形には、まだ解き明かされていない未知の表現方法があると、私はいつも思っています。
人形というと、小さいから軽いだろうと思われることがあります。ところが、60cmぐらいの棒使いの人形があるとします。胴串をまっすぐ立てて、脇を締めて、何もせずに立っているだけなら何でもありませんが、いざ動き出すと重くなります。棒の先に人形が付いているのですから、人形が前に後ろに横に傾ける場面があると、逆のてこの原理で非常に重くなります。普通は、小さな力で大きな力を発揮するというのが、てこの原理です。その大きな力が演者にかかるのです。相当腕に力がつきます。長い公演になると腕が持ちませんから、人知れずピアノ線で支えることになります。また、棒を肩や胸に乗せて、力を分散させます。棒を短く持って負担を軽くします。見た目より、人形劇は重労働です。 棒遣いの人形は、その特性から、直線的に演者の力が伝わります。すばやく人形を動かすことが出来ます。力強い動きができます。と同時に、人形にもその力が伝わるので、丈夫な人形でないとすぐ壊れてしまいます。丈夫にしようとすると、硬いもの重いものを材料に使いがちです。小さなものでも集まれば重くなります。ますます腕に力がつくことになります。紐でも太い紐を使うかもしれません。釘やビスをたくさん使うかもしれません。腕がよく動くので、力いっぱい表現したら、ピアノ線が外れたり、腕そのものが外れたりするかもしれません。どんな人形にもその特性があり、それが長所にもなり短所にもなります。私たちは、それを人形に教えてもらいながら、人形劇を作っていくのです。
|