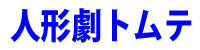
パネルシアター 紙芝居 絵本 絵話 のぞきからくり 世は歌につれ スタジオ (各種通信講座、SEO対策) ブログ「人形劇のお弁当」 リンク集 |
張子(はりこ)の人形の作り方人形劇の人形を作るとき、よく「張子人形(張り子の人形)」という言葉が出てきます。人形の型となるものに紙を何枚も貼り重ね、乾いてから中の型を抜き取って作ります。張り抜きと呼ばれることもあります。出来たものを張りぼてとか言ったりもします。一般的によく知られているものには、張子の虎(頭に触ると首が動く張子の人形)や達磨(選挙のときに当選すると目を入れたりする達磨人形)などがあります。張子は中が空洞になっていますから、虚勢を張るだけで、見かけだおしの人のたとえにも使われます。人形劇では、中が空洞になっていることが、重要な意味を持ちます。 
中が空洞になっていると、人形が軽いですから、人形を動かしている人の手の負担を軽減できます。また、中に仕掛けを作るときにも、その空洞を利用することが出来ます。イラストは、粘土で動物を作り、その動物の上に紙を貼っていくという作り方です。言い換えれば、これはペーパークラフトです。紙が乾いたら、カッターを使って中線で切り、中の粘土を抜き取り、もう一度切った部分を貼り合せます。切れ目を紙だけで貼るともろくなるので、薄い布も利用して貼り合わせをします。ということで、最初に貼るのにも、布を混ぜて貼っていくと張子が丈夫になります。 粘土に貼って中抜きをする方法だと、上に上に紙を貼るので、いくら紙が薄いからと言っても、重ねていくうちに厚くなっていきます。粘土で作った型より、少し大きめの人形が出来る結果となります。少し大きくなるイメージを持って作らないといけません。厚くなると、小さな部位は、丸みを帯びて消えていきます。そういうことを見越して、小さい部位や薄い部位は、あとから貼り付けるという作り方をします。大まかな型だけを作り、あとから耳などを付けてもいいのです。あまり細かくすると、カッターの切れ目を多く入れないと、中の粘土を抜くのが難しくなります。せっかく軽くしているのに、中の粘土が残っては逆効果になります。 粘土は、油粘土を使えばいいでしょう。紙は、和紙が最適です。そのまま貼ると、中抜きをするとき、紙が粘土に貼り付いてしまうことがあります。そのときは、粘土の表面にグリセリンや食器洗剤などを薄く塗っておきます。粘土と紙をはがしやすくなります。紙を貼るときの糊は、水のりや木工用のボンドを使います。小麦粉糊は簡単に作ることが出来て、大量に使っても経済的です。小麦粉のりを使うと、人形の内側とかにカビが生えることがあります。カビが生えないように、あとからコーティングスプレーをしておくといいでしょう。糊は組み合わせて、使うことも出来ます。なるべく紙の貼り合わせを少なくしたい、でも強くもしたいというときは、膠(ニカワ)を糊に混ぜ使います。 粘土の替わりに、発砲スチールや新聞紙を丸めて使うことも出来ます。乾いてから、中の発泡スチロールや新聞紙をかき出せば、張子が出来ます。粘土のように重たくないですから、かき出さなくてもそのまま使えます。いずれにせよ、紙を重ねることで形が膨らんでいきます。小さな人形では、思った通りの人形が出来ないことになります。そういうときには、石膏(せっこう)を使って、張子の人形を作ります。 石膏(焼石膏)は、美術教室などに石膏の像が置かれていることがあります。骨折したときなどにギブスを作るのにも使われます。骨折が治って、ギブスを取ると、内側に自分の手や足の型が残ります。その要領で人形の型を石膏で作ります。まず、粘土で人形を造形します。粘土を中線で環って、切り口を板にそれぞれ分けます。小さな部位でもちゃんとその型が取れるのが特徴です。ただ先の作り方に比べると、手間ひまかかるだけです。でも、同じものを作るときは、非常に便利です。その石膏の型だけ残しておけば、手間はずいぶん省けます。

粘土を割るときには気をつけないといけません。カッターのような薄い鉄板を利用して、割ります。早く割ろうとして、押し付けると、粘土ですからゆがんでしまいます。ゆがんだらその場で修正して、粘土を切り裂きます。人の頭を輪切りにするとき、両耳を境に切るのか、鼻と後頭部を境に切るのかでは、仕上がりが微妙に違ってきます。それは、粘土を切るときや、型を抜くときに微妙にゆがんで抜けるからです。寸分違わない型を取りたいときは、粘土を切るのをやめます。石膏は、叩き割って一回しか使わないようにします。 石膏から張子を作るのと、粘土から張子を作るのでは、紙の重ね方が逆になります。要するに、粘土からだと、最後に貼った紙が表面に来ます。表面はきれいな白い和紙の方がいいです。表面に色を塗るときの映えが違ってきます。せすから、石膏からだと先に和紙を貼ることになります。グリセリンなどを使う必要はありません。ただの水道水で第一層の和紙を貼ります。筆に水を付けて貼るとやりやすいでしょう。めくれてくる要所要所には糊を使います。第二層目も和紙を貼りますが、今度は糊を使っては使って貼っていきます。このように表面がきれいな白(和紙の薄茶)になるように貼っていきます。層が厚くなるに従い、表に出ないですから新聞紙とかガーゼとか利用して丈夫にしていきます。 土台の型が粘土ですと、しっかり貼り合せようとして強く押すと凹んでしまいます。しかし、石膏の土台は硬いので、しっかり押し付けることが出来ます。余分な糊が紙の間から出てきてつきがよくなります。ニカワを使えば、さらに薄くて丈夫な張子を作ることが出来ます。貼り終えたら、普通は天日で乾かしますが、急ぐときはコンロにかけて乾きを早めることもできます。一度しか使用しないときは、金槌で石膏を割り、何度も使いたいときは、半乾きのときに少しずつ抜いていきます。完全に乾いてからだと、抜けない部分が出てきます。抜いたら表面はのりをつけていないので、刷毛を使って丁寧に和紙を貼り付けます。 
余談になりますが、この石膏からの張子作りは、面を作るときにも利用できます。粘土で面を作り、周囲を囲って、その中に石膏を流し込みます。乾いたらひっくり返して、粘土をはがして、和紙を貼っていきます。面は立体的だと言っても、顔の表面部分だけですから、人形の張子を作るのに比べると、はるかにたやすく作ることが出来ます。石膏を割る必要もありませんから、同じお面をたくさん作るときはとても便利です。実はライブマスクを作るときも、石膏を使いその型にゴムになるメディウムを流し込みます。変装に使えるリアルな面も作ることが出来ます。また、粘土を使わなくても身近にかたどりたいものがあれば、それを張り子にすることができます。たとえば、木のお面があれば、それに和紙を貼り、張り子の複製を作ることが出来ます。胡粉(ごふん)を塗れば、さらに見事なお面に仕上がります。 人形劇「ワンワン行進曲」の人形は、頭を石膏で型を取り張子で作っています。手足は、手袋で表現しています。 人形劇「トマトの親子」に出てくるシロクマも、やはり石膏で型を取り体は布になっています。そして、どちらも顔には、布が貼られています。 人形劇「おか釣り」の人形たちは、両耳で粘土を割って、石膏の型から作っています。 人形パフォーマンス「ハロウィンダンス」のかぼちゃのお化けは、三体とも同じ石膏の型から作られ、色を変えています。 イタリアで言う"カルタペスタ"とは、張り子人形のことです。大きいのやら小さいのやらいろいろ作ります。祭のときは、山車にも使います。
|