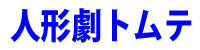
パネルシアター 紙芝居 絵本 絵話 のぞきからくり 世は歌につれ スタジオ (各種通信講座、SEO対策) ブログ「人形劇のお弁当」 リンク集 |
人形劇の音響
台詞のある人がピンマイク(pin microphone 胸元に装着する小型マイクロホン)をつけてやるのがベストです。数がないときは、固定式のもので、全員の声を拾うようマイクの設置位置を考えましょう。スピーカーより前に置くとハウリングを起こすことがあるので注意します。ボリュウムを上げすぎても起こります。本番前にテストをしておきましょう。 また観客が入ったときといないときでは音の響きが変ります。どちらかと言うと本番前は声の通りがよく感じますので、本番のときボリュウムを上げ気味にします。客席の後と前では聞こえ方が変るので、本番前に確認します。暗幕を閉める閉めないでも声の響きが変ります。幕がないところでは、残響音がすることもあります。 イベント会場などでは複数のマイクが使われていることがあります。自前のワイヤレスマイクと同じ周波数のこともあり、他の会場の声が飛んでくることがあります。持込のマイクに固執せず、その会場に常設のものがあればそれを利用します。照明も同じことが言えます。
ワイヤレスマイクには電池が使われています。人形劇の公演途中で電池切れになることもあるので、バッテリーチェッカーと予備の電池を持っておくことです。それと照明が消費電力にいちばん関係するけれど、アンプや使用する電気楽器の消費電力も把握しておきましょう。 劇団員が多いと役割を色々分担できます。少ないときは本番では担当でなくても、もしものときに担当できるようにしておきます。トラブルがあったとき臨機応変に対応できます。本番では何が起こるかわからないのですから。人形劇を中断することがあっても、全員でやれば復旧も早くなります。 照明係のことを照明さんというように、音響係のことを音響さんと言ったりします。またPAさんということもあります。PAとは、Public Address(パブリック・アドレス)のことで、マイクから入った音を拾い、チューナーやアンプへと電気的に伝わり、スピーカーから観客へと伝達とすると言うことから、その係りになった人をPAというオペレータ名で呼ぶこともあります。「音響」という難しい漢字を使わず台本には、PAとしてあることもしばしばです。 BGMを入れるか消すかをON・OFFで表わしたり、音をだんだん大きくしたり小さくしたりするとき、FI(フェイドイン)FO(フェイドアウト)を使うこともあります。舞台で使われる言葉を知っておくと、練習のときの申し送りもスムーズに運びます。 人形劇の音響について
人形劇の擬音に役立つ紙芝居の必需品
|