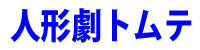
パネルシアター 紙芝居 絵本 絵話 のぞきからくり 世は歌につれ スタジオ (各種通信講座、SEO対策) ブログ「人形劇のお弁当」 リンク集 |
人形劇や人形の種類人形劇とは人形劇について書きつづってみました。まずはじめに、人形劇とは何かというと、単純に人形を遣って劇をすることです。 では、人形とは何かというと、ヒトガタと文字では書くように、人をかたどったもののことです。かたどる意味には、姿かたちを似せるということもありますが、別に人の形をしていなくても人形です。それは、人の考えや思いをかたどっていると意味において人形でありえます。 つかうには、遣うと使うがありますが、単に道具として使うのなら、使うでもかまいません。しかし、人形は単なる道具ではありません。人の考えや思いを司っているのですから、操る時間の間、心めぐらしているのですから、遣うと言いたいです。ちょっと難しいですか? その時は、使うでもかまいません。 演技をするということは、人形を操るということです。動かないという演技もありますが、通常は動くことで演技します。だから、人形劇の人形は、動いていてもひとつも恐くありません。動物の人形たちが、ぺちゃくちゃ人間の言葉をしゃべっても不思議ではありません。むしろ、楽しくもあり、それが普通です。それは、人形劇の人形がパペットだからです。 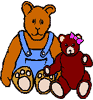
しかし、置物の人形が、動いたり、しゃべったり、髪の毛が伸びたりしたら、ちょっと気味が悪いです。それは、その人形がドールだからです。また、ドールが動いたら、パペットに近づくかというとそうではありません。おもちゃ(トーイ)に近づく傾向です。手持ちのぬいぐるみを、人形劇の人形にしようとすると、とても無理をすることになります。なかなか人形劇に馴染んでくれません。なら、最初からパペットを作ったほうが早いです。
人形劇・人形の種類結論から言うと人形劇の種類は、多岐にわたります。遣う人形によって分類されたり、そのテーマによって分けられたりします。人形の種類が混在すると、何という人形劇なのか呼び名に困ることもあります。創った原作者ですら困り、新しく造語を作ることもあります。他の人形劇とは違うんだというプライドが、そうさせることもあります。 文字からもそれぞれ違った人形劇を想像してしまします。人形劇、人形芝居、にんぎょうげき、ニンギョウゲキ、ningyougeki、NINGYOUGEKIなどなど。人形劇をやっていてもやっていなくても、違ったイメージを持たれるのではないでしょうか? 書体によっても変わります。 人形劇(有澤行書)、 人形芝居(江戸勘亭流)、 にんぎょうげき(富士ポップ)、 にんぎょうげき(恋文ペン字)、 ニンギョウゲキ(ふみゴシック)、 ニンギョウゲキ(正調祥南行書体)、 ningyougeki(Impact)、 NINGYOUGEKI(Wide Latin)などなど。 ただし、書体はパソコンによっては変化がないこともあります。 手で遣うのであれば、手遣い人形です。それで人形劇をやれば、手遣いの人形劇です。片手で遣う場合もあります。両手を使うこともあります。ピアノ線などの棒を使うこともあります。棒を主体にして動かすのであれば、棒遣い人形です。  ギニョール(フランス)・パンチ(イギリス) ギニョール(フランス)・パンチ(イギリス)
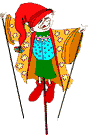 棒使い人形の作り方 棒使い人形の作り方
 指人形 玉人形 指人形 玉人形
棒は、下から操作することが多いですが、上や横から操作することもあります。いずれにしても、操作する主体が棒であれば、棒遣いの人形劇です。一部に糸を使うこともあります。糸と棒を半々に使うのであれば、棒遣いなのか糸操りなのかわからなくなります。まあ、何を使ってもいいわけです。何を表現したかが問題ですから。 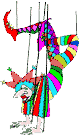 逆立ちする糸操り人形
(糸の上にはトンボがある) 逆立ちする糸操り人形
(糸の上にはトンボがある)
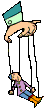
一見するマリオネットの人形操作が難しく見えるようです。しかし、やればやるほど、どれも難しさは同じに見えてきます。糸操りは、たぶんに重力を意識しないと操作や糸の張り具合の調整が難しいです。演者の手から人形が遠く離れている分、一呼吸遅れて意思が伝わるようで、不思議な動きをします。意思が流れるように伝わり始めると、離れていることを意識しなくなります。そんなところが、マリオネットを難しく見せています。 棒遣いの人形は、直接的に力強い動きを伝えることができます。迫力があると言ってもいいでしょう。手遣いの人形は、もっと直接的に動きが伝わります。ケコミの上にちょこっと見えているだけだと思っていると、人形は、明らかに舞台の上で死んでいるように映ります。マリオネットの糸の長さが、その演者にあった長さになるように、手遣いの人形も遣う人の手や指にフィットしたものになります。だから、他人の人形を遣えと言われても、動かないのは当然です。それに、人形の体の中で、どんな手の形をさせて動かしているかは秘密です。 ▼片手遣い人形の動かし方のポイント
演者の手首が、腰になります。手首は腰だという意識を常に持っていることです。そうすれば、手首だけ曲げれば、お辞儀ができます。その意識がないと、人形は倒れるようにお辞儀をすることになります。腰が意識できれば、歩くことも走ることも座ることも出来ます。一番簡単な歩き方は、例えば、下手から上手に歩くとすると、まず、客席の上手側を見ます。次に舞台の上手を見ますが、それと同時に少し上手に移動します。これを繰り返すことによって、上手に歩くことが出来ます。その時、やや人形を上下させると、もっと歩くように見えます。 次に、舞台を考えた動きを見てみましょう。客席から見えている開口の部分だけが、舞台と考えると、人形劇の舞台の中に、その物語の空間が出来ません。袖幕で見えないところから人形の演技ははじまって、退場しても完全に見えなくなるところまでを演じきります。そうすることによって、そこに存在感のある人形を客席から見てもらうことができます。 初心者の方は、セリフに一生懸命になると、人形がいつも万歳した状態になりがちです。苦しいとは思いますが、手は下に下ろしておきます。また、場面ではセリフを言っている人形に、目線をやります。セリフがない人形は、出来る限り無駄な動きをしないことです。意味のある動きなら問題ありませんが、そうでないときは、しゃべっている人形を映えなくしてしまいます。登場人物が多いと、どの人形がしゃべっているのか、わからなくなることがあります。 また、上を向いたままの人形もときどき見かけることがあります。人形の下の演者が、しんどくなってくるとそうなることがあります。人形の目線を気にしていないときにも、同じようなことが起こります。人形がどこを見ているか、常に目線にも気を使います。先に、セルフのある人形の方を見るようにとお話しましたが、完全に向くのではなく、やや客席側にも目線を投げかけるようにします。上手の人形を見るときは、気持ちは向いているのですが、舞台の上手にある人形の方を向くのではなく、客席側の上手を向きます。普段、私たちが向き合って話すようにすると、舞台では、人形が後ろ向きになっているように見えることがあります。観てもらいたいのは、お客さんにですから。 横と縦の動きについても考えましょう。横というのは、上手下手の左右の動きです。縦というのは、客席と舞台奥の奥行きの動きです。横の動きは大変目立ちます。縦は目立ちませんが、ケコミがある分、見切れてしまうことがあります。舞台は水平になっているのではなく、奥に行くほど高く八百屋になっていることを意識しておきます。
未来の人形劇抱え遣いの人形でやれば、抱え遣いの人形劇です。テーブルの上で置き人形を利用すれば、テーブル人形劇です。遣う人形や場所によっても、人形劇の呼び名が変わります。観客の参加が多いのであれば、参加型人形劇です。その人形の種類は問いません。したがって、便宜上人形劇の種類を決めているだけで、それほど重要なことではありません。もっと、重要なことがあります。 例えば、演目が変われば、それにあった舞台があるはずです。劇のテーマが変われば、舞台が変わっても何ら不思議ではありません。人形が変わっても同じことが言えます。人形と舞台、これは切り離すことのできない一体化したものです。窮屈な舞台の中では、窮屈な人形劇になります。 また、人形は、一人で一体遣うこともあれば、複数遣うこともあります。文楽のように一体を複数で遣うこともあります。文楽は、人形劇かというと、これは人形劇です。しかし、文楽をされている方からすると、文楽は文楽です。私は、人形劇の範疇に入れていますが。ということは、人形劇の捉え方は人それぞれ違っていて、人形劇の種類をいろいろ分けても、別の分け方がすぐ現れます。人形劇とコラボレーションするものによって、さらに複雑化していきます。 日本の中だけを見ていると、人形劇の世界が狭く見えることがあります。世界には沢山の国があるように、沢山の種類の人形劇があります。ベトナムには、水の上でする水上人形劇があります。水の中で操っています。村の祭りとの関係もあり、五穀豊穣を願う祭事です。たった一人にしか見せない人形劇があったり、鉄で出来た人形で重たい人形劇などもあります。鉄で出来ているのですから、火を使っても人形は燃えません。人形が出てこない人形劇もあります。人形をオブジェクトとして捉えています。それも、やはり人形劇です。考えや文化が違えば、無数の人形劇があります。 世界の人形劇を訪ねれば、 そんな世界の人形劇に出会うことが出来ます。しかし、そこに掲載されていない人形劇の方が、はるかに多いことを知っておくべきでしょう。
|