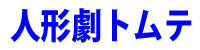紙芝居ノート5 抜き
kamishibai 紙芝居
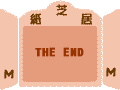
1舞台 2脚本 3絵 4台詞 5抜き 6歴史 7回想
5、抜き 
紙芝居は、演者の語りと絵の抜きの技術がすべてだと言っても過言ではありません。紙芝居が立絵から平絵に移行した時に、この抜きが重要になりました。ゆっくり抜く、早く抜く、揺らしながら、回しながら、途中で止めて抜くと、いろんな抜きかたが場面ごとに使われて、その効果を発揮します。
絵の中では登場人物は動かないでいるのに、この抜きを駆使することによって、跳んだりはねたり、滑ったり走ったり、のっしのっしと歩いたり、途中で止めることによって、絵にはない新しい場面が生まれたりします。また、数は少ないですが、絵を差し込むとか、開くとかという手法を使ったものもあります。新しい紙芝居のお話が生まれれば、そのお話にあった新しい抜きも生まれます。抜きの技術に終わりはありませんので、鏡に映したりして工夫する余地はたくさんあります。
参考:紙芝居の抜き
 生の舞台のよさ
生の舞台のよさ
紙芝居に限らず、人形劇やパネルシアターなどの舞台には、生のよさというものがあります。別にテレビやビデオなどのメディアを否定するわけではありません。それぞれの表現方法があるので、それぞれのよさがあって当然です。
まず、臨場感が違うでしょう。映画をテレビで見るより、映画館に行って、大きなスクリーンで観たほうが、迫力があり、圧倒的なその臨場感を体感できるでしょう。紙芝居や人形劇も同じです。テレビのようにその場面をズームすることはできませんが、脳の中でズームされます。生の舞台というのは、そういう不思議なことが経験できる場所です。
紙芝居のことを「昔懐かしい」と表現する方がいますが、その時、その会場で見た紙芝居というのは、何ら懐かしいものではないのです。今、現実に演じられている生の舞台なのです。懐かしさを覚えることはあっても、今そこにある紙芝居は、全く新しい紙芝居のなのです。
今の世の中は、テレビやラジオに慣れ親しんだ社会です。再放送すれば、何度も同じ映像を流せるテレビや、巻き戻せば、何度でも同じ映像を再生できるビデオとでは、生の舞台の役割は全く違います。巻き戻しはできないのです。同じように演じているように見えても、実際は違うものです。時間の巻き戻しは、生の舞台にはできないことです。ちょっと大げさに聞こえるかもしれませんが、演技者は真剣勝負と思っています。録画編集できるものと、生放送の後戻りできない緊張感は違うでしょう。
参考:生の舞台のよさとは
 チャンチキ (当り鉦) 4.5寸
チャンチキ (当り鉦) 4.5寸
鉦を鹿の角製のバチでたたく、「当り鉦」 (あたりがね) です。お囃子には欠かすことの出来ない楽器です。
さびを抑えるクリアー加工済み
底の直径: 11cm 口の直径: 13.5cm 重さ: 約650g 素材: 真鍮 (しんちゅう)
※撞木(しゅもく)、房は別売りとなります
参考:当り鉦(チャンチキ)とは
お囃子では重要な楽器の当り鉦(チャンチキ)です。真鍮(しんちゅう)を尾も主材とした金属でできています。当り鉦の呼び方は地域によりさまざまで摺鉦(すりがね)、チャンチキ、チャンギリなど、またお囃子の太鼓、締太鼓2人、笛の四人のパートを助けるという意味から四助(よすけ)とも呼ばれます。演奏方法について小さめの鉦の場合、手に持って鹿角でできたバチ(撞木)で中側をたたいたり側面をこするようにして音を出す方法や大きい鉦の場合はヒモ等で鉦を吊り下げて木槌などでたたいて演奏します。紙芝居の効果音として有用です。
真剣でやっている演技者の思いが伝わるのが、生の舞台のよさです。客席と舞台の相乗効果で、さらにライブよさが増します。とっかえひっかえできないのが、生の舞台です。テレビゲームもおもしろいですが、とっかえひっかえできるものに慣れてしまうと、命までリセットできてしまうと勘違いするかもしれません。勘違いしてしまわないように、未来のあるこどもたちには、特に生の舞台を観てほしいです。
パワーポイントで紙芝居を作ったとき
パワーポイントで紙芝居を作ると、セリフありのときは抜きを自動ですので秒数を決めなくてはなりません。しかしセリフなしのものなら、その場で語ってクリックして抜きを操作できます。その時々によって変えるなら、音声なしとありのファイルを持ち歩けばいいでしょう。
参考:パワーポイントの紙芝居は便利、Microsoft PowerPoint
紙芝居「思いやりの鬼」/パワーポイント(PowerPoint)
あらすじ
その村(大阪の茨木辺り)は昔から村人同士が仲良く、争うことなく助け合い生きていて、山の頂上には村に古くから伝わる「思いやりの鬼」という言い伝えがあり、一人ひとつずつの石を持って一緒に登り、頂上にある鬼の石像に置いて帰ると、仲良く幸せに暮らしていけると思っていた。村の人々はみんな子どもの頃に、友達と山に登り「おもいやり鬼」に石を置いているからこの村は平和なのだという。真実子はおばあちゃんにその話を聞き、友達と石を持って山に登ることになるが・・・
参考:紙芝居「思いやりの鬼」の台本
 ディスク枚数: 1
ディスク枚数: 1
レーベル: 日本コロムビア
収録時間: 39 分
「効果音セレクション」は、場面や雰囲気を表現する、おとぎ話・昔話に出てくる音、ファンファーレ・ロール・劇場・ホール・寄席 ・バラエティなどを演出。
 効果音 ベスト
効果音 ベスト
ディスク枚数: 2、149 分
レーベル: キングレコード
一人で演じるときは、なかなか効果音を使えませんが、スタッフが他にいるときは挑戦してみてももいいでしょう。
|