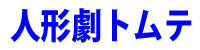紙芝居ノート4 台詞
kamishibai 紙芝居
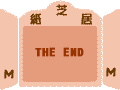
舞台 2脚本 3絵 4台詞 5抜き 6歴史 7回想
4、台詞 
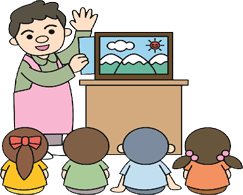 脚本と絵ができたら、下読みをしてみましょう。どの画面でどんな台詞が用意されているのか、声を出して読んでみましょう。脚本は最終的には覚える必要がありますが、覚えないうちは絵の後ろに書かれた脚本を読むのも仕方ないでしょう。しかし、客席は、紙芝居を読んでもらうことを期待しているのではありません。紙の芝居を演じてくれることを期待しているのです。ドラマが展開する臨場感を待っているのです。ですから、演者はその期待を裏切ってはなりません。
脚本と絵ができたら、下読みをしてみましょう。どの画面でどんな台詞が用意されているのか、声を出して読んでみましょう。脚本は最終的には覚える必要がありますが、覚えないうちは絵の後ろに書かれた脚本を読むのも仕方ないでしょう。しかし、客席は、紙芝居を読んでもらうことを期待しているのではありません。紙の芝居を演じてくれることを期待しているのです。ドラマが展開する臨場感を待っているのです。ですから、演者はその期待を裏切ってはなりません。
複数の演者によって演じられる紙芝居もありますが、普通、演者は一人で、台詞も一人で言うことになります。登場人物が多い紙芝居だと、七色の声を使い分けなくてはならない場合もあるかと思いますが、声を使い分けることはそう難しいことではありません。「ウサギの言うことには、・・・」とつければ、同じ声でもウサギの声とカメの声を使い分けできたりします。また、声の高い低い、ゆっくり早口を組み合わせるだけでも、四通りの使い分けが出来ます。しかし、台詞を言う時になによりも大事なのは、その登場人物の気持ちになって話すことです。そうすると、自然に声の強弱、緩急、高低が生まれます。登場人物の出身地、年齢、性格などを演出ノートに加えることによって、より確かな声でその登場人物の声を出すことが出来るようになります。また、時代物を題材にした時には、その時代背景を知ることによって、目には見えませんがその紙芝居の厚みを増すことになります。
台詞そのものではありませんが、台詞の中には間というものがあります。この間をいかに使うかによって、台詞が生きたり死んだりします。間は、何かを考えさせたり、期待させたりさせるために、台詞を言った後に一呼吸おいて次ぎの台詞を言います。この一呼吸のことを間といいます。間の時間を長くすると間延びすることになり、前後の台詞を殺してしまったり、会場にしらけたムードが漂うことになります。
あるびっくりするような場面があって、「わあーっ!」と会場がわいているのに、意味もなく次ぎの台詞を機械的に言うのは禁物です。その「わあーっ!」が終わるか終わらないかの瞬間に次ぎの台詞を言うのが効果的です。また、前場面の余韻を残したい時などにも、間をおいて次の台詞を言うのを少し遅らせたりします。テンポよく話しを進める時に、必然的に間が出来る場合もあります。例えば、次の台詞を一気に言わなければならないとしますと、大きく呼吸をしなければならないわけですが、その大きく呼吸をする時の間というものがあります。これは観客の次ぎへの期待も生まれますが、演者の一挙手一投足を見ている観客からすると、これは演者側の間です。ちなみに、間というのは紙芝居がはじまる前からあり、その間が極まって紙芝居がはじまります。拍子木が打ち鳴らされるその間と間の重なりが、紙芝居の間のはじまりかもしれません。
参考:紙芝居の台詞について
動物の音まねを楽しむ
 中根式ダイエット呼吸 ブレスティーチャー(ダイエット腹式呼吸マウスピース)
中根式ダイエット呼吸 ブレスティーチャー(ダイエット腹式呼吸マウスピース)
ドリーム (Dream)
【サイズ・重量】 約8.0X3.0X2.0cm / 約5g
【素材】 シリコーン
【セット内容】 マウスピース、中根先生監修ダイエット呼吸プログラム小冊子、携帯ケース
ここに記載されているのはほんの一部です。詳しくは紙芝居の通信講座で、解説・説明しています。もちろん講座では発声のことだけではなく、紙芝居も基礎からその応用までお話しています。受講生の紙芝居の経験年数、ご質問などにもよりますが、最終的には講座は、世界ひつしかない個別内容になります。
 キッズパーカッション キッズワダイコ レッド
キッズパーカッション キッズワダイコ レッド
客の呼び込みに
場面転換のポイントに
物語の盛り上げに
和太鼓のひとつで様々な効果音として利用できます。強弱、その強弱の連打だけでももう既に四つの効果を発揮します。
本体サイズ :W180×H80×D180mm
 1週間で効果実感! 声を出さずに歌が上達する ボイストレーニング34
1週間で効果実感! 声を出さずに歌が上達する ボイストレーニング34
長年のボーカルレッスンと15年におよぶアンケート生活習慣調査を元に、実際に高い効果をあげた物だけを掲載しております。誰でも簡単に自宅でできる、声を出さずに行うボイストレーニング、他では得られない情報が満載です。
楽譜: 224ページ
出版社: ドレミ楽譜出版社; A5版 (2013/5/1)
商品パッケージの寸法: 20.8 x 14.8 x 1.2 cm
 1週間で3オクターブの声が出せるようになる本 無理な力を入れずに声域を拡げる驚きのボイス・トレーニング(CD付き)
1週間で3オクターブの声が出せるようになる本 無理な力を入れずに声域を拡げる驚きのボイス・トレーニング(CD付き)
「声域を広げたい」というのはボーカリスト共通の願望。でも、無理に高い声や低い声を出しても、喉を痛めるだけで逆効果です。本書は、アメリカ仕込みの「最小限の力で最大限の声を引き出すテクニック」を基に、1週間で3オクターブの声が出せるようにするためのトレーニング・ブック。1日目、2日目……と、毎日のメニューをこなしていくことで、正しい発声法が身に付き、無理なく声域を広げられるようになります。
|