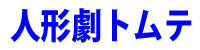
パネルシアター 紙芝居 絵本 絵話 のぞきからくり 世は歌につれ スタジオ (各種通信講座、SEO対策) ブログ「人形劇のお弁当」 リンク集 |
2、読み聞かせの要素数
絵本の読み聞かせでは、たくさんの要素が複雑に絡みあっています。初心者の話し手は、要素の多いものを選べません。たくさんの事を伝えようとすると、主題が薄れていくからです。いきなり文章の多い、心理描写の細やかなものを選ぶと、初心者の話し手は、パニックに陥るだけです。強いてはそれが、読み聞かせとしてのいい結果が得られない原因にもなります。裏を返せば、聞き手であるこどもたちにも言えることです。「話し手」の所を「子ども達」に置き換えても同じことが言えます。それは、読み聞かせを何回も経験している子と、そうでない子の差となってあらわれます。 では、「読み聞かせとしてのいい結果」とは何かというと、お話が好きになり、絵本や本に興味を持ち、子どもの生活にそれが溶け込んでいくことがその一つです。でもそういうことは、読み聞かせをはじめて間もない人に求められません。子ども達に働きかけて求める前に、まずは自分自身の身近な生活に求めます。自分にできない事、知らない事を子ども達に求めても、絵に描いたもちのようになり、その絵本の持ち味は発揮できないでしょう。むしろ逆効果になります。読み聞かせをきっかけとして、お話や絵本が嫌いになることもありえます。それは、こどもたちばかりではなく、自分自身においても。自分に出来ることを探すのです。そうして、絵本の読み聞かせの階段を一段一段上っていくのです。 絵本「おおきな木」の木は、ちびっ子に求められるものを考え、精一杯それに応えていきます。今できることを今一生懸命やるのです。そして、最後に大好きなちびっ子に出会えて、ちびっ子も大好きな木に出会えるのです。一生かかって出会いを探して、ある場所に到達するのです。絵本の読み聞かせの階段を上っても、目標の到達点はありません。出会いのあるそのときどきが、読み聞かせの到達点です。一生かけてでもできるのが、絵本の読み聞かせです。 |