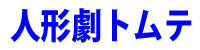5、文章のない絵本(文字なし絵本)
5、文章のない絵本(文字なし絵本)

(特徴と考察その1)
文字なし絵本の特徴
文章による読み聞かせがない絵本には、子どもの想像力をかきたてる要素が多く含まれています。文字がないから読めないというところから、絵から受ける印象や思い浮かんだことを組み立てて想像するのです。では、語り手は、「どんなふうに読むんですか?」ということが問題になります。文章がない分、語り手がコメントを入れながらアレンジもできるという利点があります。それには、語り手にまず想像力を付けておかないといけません。
ページをめくって絵を見ていくと、文章がないのにそこにストーリーがあるものがあります。そのような絵本は、そのストーリーに肉付けをして文章にしていけば、文章がなくても読み聞かせが出来ます。自分が想像したものを、文章にして伝えるだけでもいいのです。もしストーリーがなければ、どうすれば良いのか。実はそのような絵本でも、平気で読んでいる子ども達の姿を見かけます。そこにストーリーがあって、説明しようとするから、ストーリーがないと思うのであって、説明しようとしなければ、そこにストーリーは存在します。見るこどもの力を借りて、読み聞かせをします。こどもたちに感じ取ってもらうことが、ストーリーのない絵本の読み聞かせになります。文章のある絵本でも、その文章が絵本の絵の説明ではないとわかっていれば、このことが理解できるでしょう。
(特徴と考察その2)
文章がないので、話し手が話さないといけないのが、この絵本の読み聞かせの特徴です。だけど、それをこどもたちが聞いてくれるかどうかの保障はありません。絵本に文章があってもなくても、こどもたちが聞いてくれるかどうかは、話し手と聞き手との信頼関係があるかどうかによります。信頼している人の言葉は心地よいものです。母親が子どもを膝に抱いて、読み聞かせをすれば、安心して聞いてくれるでしょう。そのような信頼関係を持つのは、子ども達と一緒に遊ぶことが信頼関係を作る一助になります。ですから、その日はじめてあった子に、この絵本の読み聞かせをするのは非常に難しいです。
(特徴と考察その3)
こどもたちは絵本の絵を見ているけれど、目に映ったものを理解しているかどうかはあやしい。加えて、その絵本の本質的なことが見えているかどうかも。文字なし絵本に慣れないうちは、本質的なことは、何度も繰り返さないと、話し手が誘導してやらないと、見えてこないものです。繰り返すことによって、こどもと一緒にいろんなことを発見します。それには、やはり話し手がその絵本についての背景とか含めて、すべてを調べ上げた上で、その絵本の読み聞かせをやるというプロセスに移るべきです。
文章がなく補足的な語りをつけたとしても、文字なし絵本は耳からの情報量が極端に少なくなります。そこで問題にしたいのは、注視点と注視時間です。大人とこどもでは違いますが、もしこどもだったら、どこに注目して、どの部分に見る時間を取るのかを探ります。話し手を聞き手では、倍くらいの時間が必要だと思ってください。どこに注視するかは、本番のそのときにこどもの目線に注意をはらいます。また、息づかいにも注意を傾け、読み進めます。いきなりこのようなことは出来ませんので、文章のある絵本の読み聞かせのときに、客席と息づかいを感じながら、読み進めます。そのときの経験が、ここでは活きてきます。
参考:子どもの力を借りる
子どもが絵本に飽きてしまった時
<注視点と注視時間>
絵本の絵のどこに子どもが、興味を持つのか(注視点)、どれだけの時間、その絵に興味を持つか(注視時間)は、その子の興味や年齢によっても違いますが、概ね、大人の2倍の注視時間がかかると思っていいでしょう。それゆえ文章を読み終えたからといって、すぐに次のページをめくるのは早計です。
<絵本から絵画、童話への移行>
絵本の絵を言葉に換えるとき、言葉にならない絵は永久に絵として表現されます。その絵本の絵は、絵画につながっていきます。また、絵本の絵を言葉に換えるとき、言葉に置き換わる絵は、言葉の方がよりよい表現力を持っていれば、その絵本の絵は、言葉から童話につながってきます。
 絵のない絵本 (若い人の絵本)
絵のない絵本 (若い人の絵本)
By 山室 静, 岩崎 ちひろ, アンデルセン
町の狭い小路の片隅の貧しい青年の部屋に、月の光はさしこんで話をしてくれました。その日の夕方や前の晩に見たことなど、月から聞いた33の話。詩情豊かに、人々の気持ちをやさしく包んでくれる。
単行本: 90ページ
出版社: 童心社 (1966/11/25)
商品パッケージの寸法: 20.6 x 18.8 x 1.6 cm
|