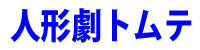10、アイテムの違い
10、アイテムの違い
広がる絵本の世界
一つの物語があり、その内容を伝えるものが絵本であれ、紙芝居であれ、どんなアイテムで伝えるかは、それぞれに特徴があります。下の表は、一般的な分類による違いです。例外的なものや分類上相互に融合しているものなどは、この限りではありません。細部の類似部分については、ここでは述べていません。言い換えると、ひとつのお話を全く同じ内容なのに、映画やテレビドラマ、舞台、アニメなどに表現方法を変えたとき、それぞれの特徴で違いが生まれます。
| Item | 絵本 | 読み聞かせ | 紙芝居 | 絵話 | 素話 |
|---|
| Relations | 作者-読者 | 話手-聞手 | 演者-観客 | 話手-聞手 | 話手-聞手 |
| Transmission | 黙読 | 音読 | 台詞 | 語り | 語り |
| Sense | 触・視 | 聴・視 | 聴・視 | 聴・視 | 聴 |
| Object | 個人 | 個人・複数 | 複数 | 複数 | 個人・複数 |
| Medium | 絵・文字 | 絵・話 | 絵・話 | 絵・話 | 話 |
| Necessity | 絵本 | 絵本 | 絵・舞台 | 絵 | なし |
外掘りを埋めると
絵本の読み聞かせについて、10番目に当るこの項目です。このあたりになると、話し手の経験、練習量、取り組む姿勢によって、絵本の読み聞かせの出来不出来がはっきりしてきます。時には絵本の読み聞かせの若い番号に立ち戻ることも大切です。また、絵本、読み聞かせ、紙芝居などの違いを知っておくと、絵本の読み聞かせのコツや注意点が分かり、その導入のねらいが明確になってきます。
最初の取り組み
最初は、登場人物が少なく、文章も少ないものから取り組んでいけばいいでしょう。だんだん登場人物が多く、文章も多いものに移行していきます。そのとき困るのが、登場人物が多きことでパニックになりそうになることです。その戸惑いは、聞き手にも反映されます。そこで、独り人形劇でいう役作りをします。一人で演じるのですから、登場人物を演じ分けないと、観客にはわかりづらい劇になります。もともとの声は一人です。七色の声を使い分けても、限りがあります。そこでやるのは、登場人物の背景を設定して、絵本には書かれていない人物像を自分の中に作ってしまうことです。それが出来れば、同じ声でも、個々の人物がそこに存在して、話しているように聞こえます。登場人物がたくさん出てくる落語のようなものです。一人で使い分けすることが出来ます。もちろんこれは、登場人物が少なくてもやっておいていいのです。
さりげない素振り
台詞の中のキーワードを伝える工夫も大事ですが、言葉だけに頼るのではなく、話し手は体をさらしているのですから、自然な身振り、手振り、表情などをくわえて、言葉以上のもので絵本の読み聞かせをします。ただし、大げさな動作は芝居になってしまい逆効果になってしまいます。あくまで自然な流れの中で行ないます。それを理解できないうちは、身振り手振りなどは一切行ないません。
|