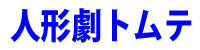
パネルシアター 紙芝居 絵話 のぞきからくり ストーリーテリング スタジオ (各種通信講座、SEO対策) ブログ「人形劇のお弁当」 リンク集 |
8、なぞなぞやクイズの要素(こどもの「なぜ」)
物語というと構えてしまう子でも、自分の日常生活にかかわりがあるものが出てくると、すっと物語に溶け込むことが出来ます。たとえば、話の中になぞなぞのようなクイズ的なことがあると、そのお話もそのなぞなぞも解き明かしたいという気持ちで、その物語を楽しみます。物語へ入り込む要素は、別の角度からのものであってもいいのです。大人で言えば推理ドラマを見ているようなものです。犯人は誰だ?動機は何だ?といった具合に。 絵本の中のなぞなぞばかりではなく、話の内容そのものが、こどもたちにとってはなぞなぞになることがあります。読み聞かせをしているとき、ぼそぼそと聞こえない程度に疑問を投げてくるのならまだしも、会場のみんなに聞こえるような声で問いかけてくることがあります。その問いかけに答えるべきか、無視するべきかは、話し手が瞬時に判断しなければなりません。その問いかけがきて、子どもとキャッチボールができるかどうかは、非常に経験がものをいいます。 その子の疑問は、そのとき本当に聞きたかったことなら、答えてやらないと、無視されたと思うかもしれません。物語に入り込んで、思わず出た言葉なら、答えなくても絵本ライブのよさがそこに出ているといえます。何も答えを聞いているのではないのですから、答えても答えなくても絵本の読み聞かせは良い方向に展開します。むしろ答えず間で答えるほうが、臨場感を生みます。 こども達の質問には、その場で答えるか、読み聞かせを終えたあとで答えるかは、絵本のストーリーの腰を折るかどうかで判断します。話から脱線するようならあとで答えます。そのことを伝えておくと、何度も質問をされなくて済みます。読み聞かせのストーリーの一環となるなら、その場で答えます。この場合、話し手の人生経験が関係してきます。どれだけ、多くの答えを用意できているかによって、客席とキャッチボール出来るかが違ってくるからです。今一度思い出してください。読み聞かせの大きな柱は、聞き手・話し手・絵本です。話し手も大きな柱になる要素なのです。ただ、絵本の内容を代弁する要素なら、大きな柱にはなりえないのです。 子どもの「なぜ」「どうして」参考:なぜ雪は白いのか どうして服を着るの どうしてご飯を食べる大人は質問されると、つい左脳で考えたことを答える傾向があります。教育的な絵本の読み聞かせならそれでもいいでしょうが、擬人化された主人公が登場する絵本なら、右脳で考えたことで答えます。そして、こどもたちの「なぜ」は、大人の「なぜ」とは違うことを理解しておく必要があります。その子の「なぜ」は、その子の周りになるものを参考にして「なぜ」が生まれてきたものです。身近な「なぜ」なら身近な「なぜ」で返してあげます。それが、こどもたちの「なぜ」に対する答えです。ただそれが正しい答えであるかどうかはわかりません。話し手の感性が多分に反映するからです。
話し手の感性を磨くには、こどもたちの「なぜ」が詰まっている本が参考になります。このページで生まれた疑問も、 「かみさまへのてがみ」や「サンタクロースっているんでしょうか?」などが、解いてくれるでしょう。 |