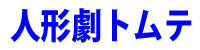
パネルシアター 紙芝居 絵話 のぞきからくり ストーリーテリング スタジオ (各種通信講座、SEO対策) ブログ「人形劇のお弁当」 リンク集 |
6、親しみやすい絵 |
|
絵本の読み聞かせの留意点
3 絵本の文章の量 4 登場人物(右脳左脳) 5 文字なし絵本 6 親しみやすい絵 7 物語のリズム(様式化) 8 クイズ的要素 9 推理的要素 10 アイテムの違い 11 心理描写 12 作者の思想や哲学 13 作品の前後 14 プログラム(音読と黙読) 15 最後に |
こども絵本ガイド
絵本は、親からこどもへの心の贈り物。
|
6、絵が親しみやすい絵本の絵は、対象となるこどもたちの年齢層にあっているかが問題になります。一般的に絵画的な、かつ線が細く複雑になったものは、年齢層が高くなります。その絵を素直に取り入れるには、経験が必要だからです。単純で線や形が素朴であるなら、年齢層が低くても理解しやすい絵になります。人形で言うなら、リアルな人形より、デフォルメされた人形が、幼い子には向いています。題材も子どたちの身近なものが取り上げられていれば、親しみやすくなります。 また、色も混色を多く使用するより、原色に近いものの方が、幼子にとってはとらえやすい色になります。国や文化によって色相が違うので、色使いが統一されていることも、違和感なく見ることができる絵となります。デフォルメされて要点が簡潔に描かれていれば、それとあいまって文章も簡潔でわかりやすい文章になります。絵と文章は別のものですが、絵と文が織り合った絵本が、親しみのある絵本となります。 絵本「びりびり」は、モノクロの絵本で、飾りのないシンプルな絵が特徴です。赤ちゃんが、手に触れたものをなめたり、ビリビリくしゃくしゃにしたりすることがあります。そのいちばん原始的ともいえる本能の動きが、絵本になって表現されています。この純粋な感情の動きは、国や文化の違いを意識させないものです。こどもたちだけじゃなく、純粋な気持ちを忘れてしまった、大人たちに読み聞かせしても面白いかもしれません。 Baby Laughing Hysterically at Ripping Paper
|
|